
自治体や公共的団体主催の講演会や研修会で、1月に弊社へ講演のご依頼をいただいた講師の方々を一部ご紹介いたします。
(*講師方のお立場やご事情等によりHPや講師ガイドブックではご紹介出来ない方もいらっしゃいますので、公開如何に関わらず気になる講演講師の方についてはお気軽にお問合せください)
18歳になったら『出来ること』と『その責任』
~SNSを介した闇バイトとは~
 森 雅人 もりまさと
森 雅人 もりまさと
一般社団法人刑事事象解析研究所(ケイジケン) 代表理事
警察の元警部補。サイバー犯罪、経済犯罪、薬物銃器犯罪等を扱う生活安全部門の刑事を約15年担当。警察で経験した事例を交えながら、高齢者向け「悪質商法の対処法」、経営者向け「炎上・風評被害対策」、学生・児童向け「SNSの正しい使い方」など、対象者に応じた幅広いテーマで講演。
成年年齢引き下げに伴い、一人の大人として自己責任の下に出来ることが広がる半面、責任が伴うことを知らずに、余計なトラブルや犯罪に巻き込まれることが想像されます。 そうした事態を未然に防ぐためのポイントを… (続きを読む)
生きることは感動すること
~柔らかな心で明日を生きてみませんか?~
お話と歌と朗読劇で心のストレッチ
 佐久間レイ さくまれい
佐久間レイ さくまれい
声優・歌手・劇作家・作詞家
アニメ「それいけ!アンパンマン」バタコ、「NHKきょうの料理ビギナーズ」高木ハツ江、「魔女の宅急便」ジジの声でおなじみの声優であり歌手。脚本家としては命や日常をテーマにした朗読劇などを執筆し、自ら語る活動を展開。
<講演の流れの一例> 【挨拶&自己紹介】 キャラクターの映像を使って声を披露&自己紹介(パワーポイント) 【歌】 「アンパンマンのマーチ」「ふるさと」など 【トーク】 身体同様、心も何かにつま… (続きを読む)
保護者との良好な関係性を構築する
~普段からできること~
 岩田 大 いわただい
岩田 大 いわただい
こどもと学び 大研究所:代表
保育者養成校非常勤講師(3校を兼務)
保育士、保育士養成校教員・学科主任、保育園施設長、保育士等キャリアアップ研修講師(法人・自治体)など、保育に携わり18年。2023年、子ども・保育者・保護者みんなの心が躍動する保育や子育てを考える[こどもと学び 大研究所]を設立。保育や子育て研修や次世代保育者育成など多方面に活躍中。
テーマは保護者となっていますが、対人援助職であれば人と関わることは不可欠です。 日ごろからの意識で大きく保護者との関係性がより良くなっていきます。 入園前・今すぐ・日頃から、保育者としてどの様なかかわ… (続きを読む)
住民自治によるまちづくりの視点
~孤独死ゼロへの大山自治会の挑戦~
 佐藤良子 さとうよしこ
佐藤良子 さとうよしこ
東京都立川市大山自治会相談役
東京都立川市大山自治会長を15年間務め、現在は相談役。在任中に自治会加入率100%、自治会費回収率100%、孤独死ゼロ、格安自治会葬を手掛けるなど、そのアイデアと行動力で「日本一の自治会」と称される自治会を育て上げた。これからの地域づくりのヒントになればと各地で講演を行っている。
私は50歳代で自治会デビューのきっかけは、たまたま夫の代理で会計監査をしたことでした。その時に次のような4つの疑問があり自治会活動を始めました。 ①このままの自治会活動を続けて、本当に住民にとって必… (続きを読む)
子どもの心を育てよう!
 湯浅正太 ゆあさしょうた
湯浅正太 ゆあさしょうた
一般社団法人Yukuri-te 代表理事
イーズファミリークリニック本八幡 院長
小児科医として子どもの心のケアも含めた支援を行うと共に、「親子の心のきずなを深め、豊かな子どもの心を育める社会」を実現すべく(一社)Yukuri-teを設立。障がい(発達障がい・知的障がい・身体障がい等)、子どもの人権、いじめ・不登校問題にも深く心を寄せ、作家・講演・各種メディアなど多方面に活動。
さまざまな境遇の子どもたちの支援に携わってきた小児科医としての経験、そして子どもの心を言葉で表現できる作家としての経験をもとに、子どもの心の育て方をお伝えしたい。 少子高齢化・人口減少により大きく変わ… (続きを読む)
孤立と虐待のない街づくり
~傷つく子どもを支えるためにできること~
 石川結貴 いしかわゆうき
石川結貴 いしかわゆうき
ジャーナリスト
家族・教育問題、青少年のインターネット利用、児童虐待、子どもの貧困、ヤングケアラー、介護問題などをテーマに取材。豊富な取材実績と現場感覚をもとに、多数の話題作を発表。出版のみならず、専門家コメンテーターとしてのテレビ出演、全国各地での講演会など幅広く活動中。日本文藝家協会会員。
増加の一途を辿る児童虐待。悲惨な状況を防ぎ、子どもたちの健やかな成長を見守るためにいったい何をすればいいでしょうか。 親の育児不安や経済的困窮、人間関係の希薄化など虐待の背景は複雑です。まずは現状を認… (続きを読む)
近年の災害に学ぶ ~これからの地域防災の在り方~
 尾下義男 おしたよしお
尾下義男 おしたよしお
危機管理アドバイザー
精神対話士、防災士
消防庁で27年間勤務。阪神淡路大震災も経験し、専門的立場から、災害の恐ろしさや、災害が引き起こす心のストレスなど、一人一人の防災に対する意識改革の重要性を説く。また、大学院で危機管理学を研究するなど、精神対話士として心に傷を負った方のボランティア活動も行っている。
加入率低下、担い手不足解消!
令和に求められる自治会・町内会の運営や活動
 水津陽子 すいづようこ
水津陽子 すいづようこ
合同会社フォーティR&C 代表
経営コンサルタント
地域活性化・まちづくりコンサルタント
自治会・町内会の活性化などの共助コミュニティの再生、持続可能なまちづくりがテーマ。それぞれの地域で抱えている現状と課題、解決法など、他にはない具体的な事例を交えた分かりやすい講演が好評。著書『めざせ、担い手不足解消!自治会・町内会負担軽減&IT活用事例ブック』(実業之日本社)など。
今こそ、若い世代が多数参加する運営と活動に転換するアイデア・ヒント、先進事例を紹介します 1.時代の変化、今の住民ニーズにマッチした運営、活動とは 若い世代が加入しない理由、参加したい活動、運営スタ… (続きを読む)
『コニタンの闘病日記』
~すべての人々へ感謝の心を~
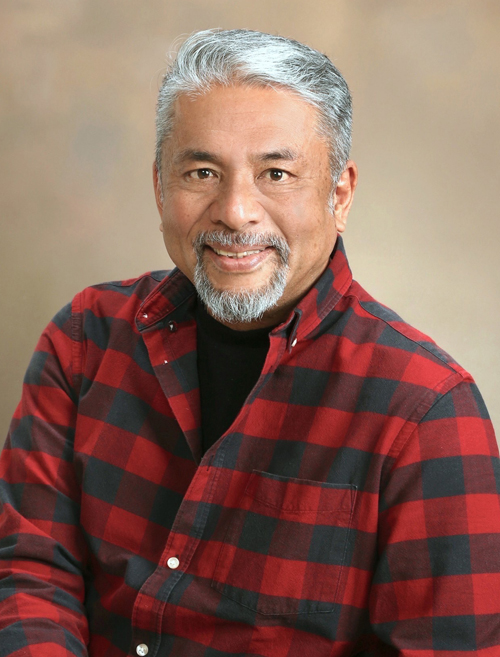 小西博之 こにしひろゆき
小西博之 こにしひろゆき
俳優
“コニタン”の愛称で親しまれ、欽ちゃんファミリーの一員として人気を博す。2005年に腎臓癌の大手術を受け、90日間にわたる壮絶な闘病生活を経て、現在は仕事を行えるまで回復。支えてくれた方への感謝と、前向きに生きることの大切さを強く実感し、トークショーや講演などで励ましと希望を与えている。
末期癌との壮絶な闘いから、欽ちゃんファミリーのオーディションに受かったきっかけ、欽ちゃんの考え方から教わったこと、私が実践している人生の4つの基本などをお話しします。 人生は予期せぬ不幸に見舞われます… (続きを読む)
一歩一歩の健康づくり
 増田明美 ますだあけみ
増田明美 ますだあけみ
スポーツジャーナリスト
大阪芸術大学 教授
高校在学中、長距離種目で次々に日本記録を樹立、1984年ロス五輪出場。現在はスポーツジャーナリストとして、執筆活動、マラソン中継の解説に携わる。その他、講演、イベント、テレビ出演、ナレーションなど多方面で活躍。日本パラ陸上競技連盟会長など公職も多数務めている。
らんま先生“環境エコ・パフォーマンスショー”
~パフォーマンスで環境へのメッセージを伝える~
 らんま先生 らんませんせい
らんま先生 らんませんせい
eco実験パフォーマー
環境問題と科学実験、パフォーマンスを融合した「eco実験パフォーマンスショー」。身近なものを使って実験を行い、知識より知恵の大切さを学んでほしいと、ユーモアのあるトークでエコの大切さを伝える。体験した子どもたちからは「もっと地球の環境について考えてみたいと思った」との声が数多く届いている。
子どもからおとなまで、学校の理科室にタイムスリップしたような、どこか懐かしく、ユーモアを交えた温かい雰囲気のパフォーマンスショー。 教師をしていた頃から、「地球環境を守るために、環境保護の重要性をも… (続きを読む)
鶴英の介護講談
ほっとけ 心でアッパレ介護
 田辺鶴英 たなべかくえい
田辺鶴英 たなべかくえい
講談師
創作講談で人気の女流講談師。子育てが一段落した90年、田辺一鶴に入門したという変わりダネ。実体験(実母・義理母・義理父の介護)を基にした介護講談は、「共感できるところが多い」「説得力があり介護に対する考え方が変わった」等の声が寄せられる。他に、自閉症講談、リサイクル講談、防災講談等。
実母、義母の介護体験から、安心して老いる方法、その秘訣を伝授する講談。 介護は女の仕事という古い考えの男性に、良い薬になる話しです。 親の介護をひとりで抱え込むと、自分も倒れてしまうという悲劇が待っ… (続きを読む)
タネと食と命と人権
 鈴木宣弘 すずきのぶひろ
鈴木宣弘 すずきのぶひろ
東京大学大学院 農学生命科学研究科 特任教授・名誉教授
農学博士
農業経済学の第一人者として安全な食を支える農林水産業の振興と地域の活性化に尽力。「食の海外依存と安全性の懸念」「畳みかける貿易自由化と安全保障」「環境負荷を改善する循環型農業」「命・環境・地域を守る生産から消費までの双方向ネットワーク」「協同組合の使命」など研究領域は多岐にわたる。
ジャパンルネッサンス
~今こそ日本の底力を見せるとき~
 呉 善花 おそんふぁ
呉 善花 おそんふぁ
評論家
東京国際大学 教授
韓国(済州島)出身の評論家。来日後、大東文化大学、東京外国語大学大学院で学ぶ。拓殖大学教授を経て、2022年より現職。著書『攘夷の韓国 開国の日本』は山本七平賞を受賞。『反目する日本人と韓国人』(ビジネス社)、『謙虚で美しい日本語のヒミツ』(ビジネス社)など著書多数。
■韓国で受けていた教育と、来日して知った実際の日本とのギャップ。 ■韓国、中国で反日感情が盛り上がる理由とは? ■歴史認識に対する考え方、向き合い方の違いとは? ■日韓、日中関係の根底にあるものとは?… (続きを読む)
学習障害から考える共生社会
~多様性を大切にする未来へ~
 南雲明彦 なぐもあきひこ
南雲明彦 なぐもあきひこ
明蓬館(めいほうかん)高等学校
共育コーディネーター
21歳の時にLD(学習障害)の1つであるディスレクシア(読み書き障害)であることがわかる。高校時代より不登校、引きこもり、うつ病など、様々な経験をする。子どもがSOSを出せて、そのSOSを大人が見逃さないために何ができるのか。全国各地で講演をしながら、対話を続けている。
21歳で学習障害とわかってから、「障害」や「健常」について考えるようになりました。「普通」という目に見えない物差しで人をはかり、「この人は普通」「この人はそうじゃない」と判断してしまうと「同じ人間であ… (続きを読む)
「振り返りが保育の質を高める」
~0歳から5歳までのつながりのある保育~
 井桁容子 いげたようこ
井桁容子 いげたようこ
乳幼児教育実践研究家
保育SoWラボ代表
非営利団体コドモノミカタ代表理事
東京家政大学ナースリールーム主任、東京家政大学非常勤講師を歴任。2018年4月よりフリーとなり、 保育SoWラボ(ほいく そう らぼ)代表、非営利団体コドモノミカタ代表理事、保育の根っこを考える会主宰。
全国私立保育連盟『保育通信』に連載中。メディア出演、子ども向け番組の監修など多方面で活躍。
上を向いて生きる
 宮本亞門 みやもとあもん
宮本亞門 みやもとあもん
演出家
演出家として、ブロードウェイやウエストエンドなど世界的に活躍。親しみ感のあるタレント性も兼ね備え、テレビ番組にも多数出演。印象とは反対の紆余曲折した生き方は、多くの人から共感を得ている。講演では、固定概念にとらわれない、亞門流のコミュニケーション術、スランプの乗り越え方を伝える。
2019年のテレビの企画から前立腺がんが判明し、全摘出手術を受けました。後遺症にも悩まされながらも、がんと向き合った日々を著書「上を向いて生きる」でも赤裸々に綴っています。2011年には最愛の父が他界… (続きを読む)
実り多い豊かな人生 私は創造的でありたい
 若宮正子 わかみやまさこ
若宮正子 わかみやまさこ
ITエバンジェリスト
エクセルアートの創始者。58歳からパソコンを独学で習得し、2017年にゲームアプリ「hinadan」を公開。
2017年より政府主催会議の構成員を多数務め、現在は、内閣府主催「高齢社会対策大綱策定のための検討会」構成員、デジタル庁デジタル社会構想会議構成員など。IT分野において広く活動している。
人間が人工知能(AI)とどう付き合っていくか。 それは、創造する、新しいことに挑戦すること。 これは、やはり人間にしかできないことだと思っています。 そして、人生100年時代を生きるために必要なのは… (続きを読む)
生成AIの衝撃!人工知能時代をどう生きるか
 室山哲也 むろやまてつや
室山哲也 むろやまてつや
日本科学技術ジャーナリスト会議会長
元 NHK解説主幹
NHK「クローズアップ現代」「NHKスペシャル」のチーフプロデューサー、解説主幹などを歴任。また、子ども向け科学番組の塾長として科学教育にも取り組み、科学や技術と社会との繋がりについてわかりやすく解説。その他のテーマに「どうつくる?持続可能な社会」「再生可能エネルギーと未来社会」など。
Chat GPT(チャットGPT)をはじめとする生成AIが、世界を揺るがしています。多くの企業や団体が利用をしはじめ、日本のみならず世界の経済や社会に大きな影響を与えています。また、既存の雇用を奪い、… (続きを読む)
子どもの <いのち> を守る保育のために
 猪熊弘子 いのくまひろこ
猪熊弘子 いのくまひろこ
ジャーナリスト
駒沢女子短期大学 教授
日本女子大卒後、高校教諭を経て、ジャーナリストに転身。主に就学前の子どもの福祉や教育、安全教育などを中心に取材・執筆。その後、都内の副園長を経て、駒沢女子短期大学保育科教授。ジャーナリストとしても取材・執筆、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、講演・研修など、幅広く活躍中。
重大な事故や虐待を防ぐためにも、日ごろから保育士同士がコミュニケーションをとることが必要です。 子ども主体の保育をしていれば、不適切になりようがない。 こども主体の保育っていうのは、わがままだとか、… (続きを読む)
学ぶ意欲が湧き出る授業
~幼保小連携でつなぐ育ちと学びの探究~
 奈須正裕 なすまさひろ
奈須正裕 なすまさひろ
上智大学 総合人間科学部教育学科 教授
国立教育研究所室長、立教大学教授などを経て現職。専門は教育心理学、教育方法学。長年の研究を基に具体的な事例を交えた講演は、教育現場においても高い信頼を得ている。主な著書に『個別最適な学びと協働的な学び』(東洋館出版社)、『個別最適な学びの足場を組む』(教育開発研究所)等多数。
AIに負けない力
~非認知能力は遊びを通して育まれる
 内田伸子 うちだのぶこ
内田伸子 うちだのぶこ
IPU・環太平洋大学 教授
お茶の水女子大学 名誉教授
十文字学園女子大学 名誉教授
発達心理学、言語心理学、認知科学、保育学が専門。長年、ベネッセ「こどもちゃれんじ」の監修に携わり、NHK「おかあさんといっしょ」の番組開発・コメンテーターなども務める。子どもの発達段階に着眼し、分析データを基に、子どもの言語発達・認知発達をより良くする具体的な教育法や援助の方策を説く。
新保育所保育指針で改定された「非認知能力」を、エビデンスに基づきお話させていただきます。 保育関係の各研修会で喜ばれている内容です。 ※内田先生の著書『AIに負けない子育て ~ことばは子どもの未来を拓… (続きを読む)
保育園の危機管理と災害対応
~保育士と園児を守る手法と対策~
 サニーカミヤ さにーかみや
サニーカミヤ さにーかみや
元 福岡市消防局消防吏員、レスキュー隊員、ニューヨーク州救急隊員、
国際緊急援助隊隊員、一般社団法人日本防災教育訓練センター 代表理事
国際レスキュー隊として、34ヶ国5000件の災害現場救助活動と消防・防災事情を調査。人命救助者数は1500名を超える。防災意識向上やBCPやパワハラ防止などの防災教育講演を、日本国内の大企業では200社以上、自治体では約100市町村以上行っている。著書『いざというときの自己防衛マニュアル』等。
子どものコミュニケーション力を育もう
子育てが楽しくなる 子どもの心に届く言葉かけ
 天野ひかり あまのひかり
天野ひかり あまのひかり
NPO法人親子コミュニケーションラボ 代表理事
NHK「すくすく子育て」 元 キャスター
親子コミュニケーションアドバイザー / フリーアナウンサー
NHK「すくすく子育て」のキャスター(2005~08年)を経て、現在は、NPO法人親子コミュニケーションラボ代表理事、親子コミュニケーションアドバイザーとして、親子向けのトークショーやコミュニケーションに関する講演会など多方面で活躍。著書『子どもを伸ばす言葉 実は否定している言葉』など。
「コミュニケーション力」を高めることは「生きる力」を高めることに通じると思います。 そんな力を持った子どもたちを育てるためにお母さんお父さんにできることは、、、 【お子さんの心に届くことばで話しかけ… (続きを読む)
「働き方改革」の推進
~多様性を活かすこれからの職場とは~
 宮原淳二 みやはらじゅんじ
宮原淳二 みやはらじゅんじ
株式会社東レ経営研究所 DE&I共創部長
資生堂に21年間勤務し、営業、商品開発・マーケティング、労働組合専従、人事部など様々な業務を経験。中でも人事労務全般に携わる期間が長く、人事制度企画から採用・研修まで幅広く担当。行政、民間企業等でワークライフバランス、ダイバーシティ、業務効率化などをテーマとした講演を多数実施。
ダイバーシティマネジメントの基本的な考え方について理解できる 多様性を活かす職場にするために労働組合として出来ることを考えられる 1.ダイバーシティマネジメントとは ・Diversity Inclu… (続きを読む)
良い人間関係、効果的なコミュニケーションの仕方
~相手と心を通わせる~
 松本 純 まつもとじゅん
松本 純 まつもとじゅん
親業訓練インストラクター
コミュニケーショントレーナー
ADHDの息子を持ち、家庭崩壊の寸前までいった母親としての経験を基に、子育てに悩む親たちを支援。親と子の愛情をどう育むか、効果的なコミュニケーションの方法を具体的に伝授。「親が愛情だと思っていても、子どもに伝わらなければ同じこと」と語り、親子関係の再生に向けて一筋の光を投げかける。
良い人間関係は築く事ができます。ゴードン・メソッドを使って、効果的なコミュニケーションが気持ちの行き違いや誤解のない良い関係を築く事を体験学習で学んでもらいます。 コミュニケーションの基本から、実際に… (続きを読む)
AIがもたらす未来
~人工知能の現在とこれからの社会~
 池谷裕二 いけがやゆうじ
池谷裕二 いけがやゆうじ
東京大学 薬学部 教授
薬学博士、脳研究者。神経の可塑性を研究することで、脳の健康や老化について探求。日本学術振興会賞、日本学士院学術奨励賞他、受賞多数。『脳には妙なクセがある』(新潮社)『パパは脳研究者』(クレヨンハウス)『できない脳ほど自信過剰』(朝日新聞出版)等著書多数。
人工知能によって人々の生活はどのように変わるのでしょうか。 ヒトの脳機能はどこまで人工知能で置き換えられるでしょうか。 人工知能が進化したら人の権利は侵害されるでしょうか。 講演会では私自身の研究の… (続きを読む)
地域や住宅の防犯対策 安全・安心に暮らしたい!
これだけは知っておきたい!その必須ポイント
 京師美佳 きょうしみか
京師美佳 きょうしみか
防犯アドバイザー
犯罪予知アナリスト
女性ならではの視点で安心を届ける防犯アドバイザー。住居、ビル、店舗、街頭、ネット、盗聴・盗撮、ストーカー、学校、子ども、医療機関など、あらゆる場所の防犯対策に対応。具体的な事例を交えた講演は「わかりやすい」「すぐに役立つ」と好評。著書『60歳から絶対やるべき防犯の基本』など。
システムだけで解決できることではなく、環境や、各自の心掛けなど、押さえておくべきポイントをお伝えします。 ポイントのいくつかでも実行していただくことで、安心できる快適な空間で過ごしていただけます。 【… (続きを読む)
創作あそび研修
 たにぞう たにぞう
たにぞう たにぞう
創作あそび作家
OFFICE TANIZOU代表
保育士を経て、フリーの創作あそび作家に。子育て雑誌、新聞、保育雑誌にあそびやエッセイなど執筆中。 NHKEテレ「おかあさんといっしょ!」に楽曲提供多数。主な作品「ブンバ・ボーン!」「バスにのって」「でかけよう」「しゅりけんにんじゃ」など。NHK「ダーウィンが来た!」の動物カメラマンとしても活躍中。
夢をあきらめない
 石黒由美子 いしぐろゆみこ
石黒由美子 いしぐろゆみこ
北京五輪アーティスティックスイミング日本代表
幼少時に交通事故に遭い、 顔面を540針も縫う大怪我を負う。 その後、後遺症に苦しみながらも希望を失わずアーティスティックスイミングに打ち込み、見事北京五輪出場という夢を果たす。講演では、これまでの体験を基に、感謝の気持ち、夢をあきらめずに努力を継続させることの大切さなどを伝えている。
小学校2年生のときに交通事故に合い、大きな障害を負いました。 しかし、入院中のベットで、「シンクロでオリンピックにでる!」という夢を掲げ、退院後、母との2人3脚で様々な障害を乗り越えてきました。17… (続きを読む)
自治体・公的団体・医療福祉・学校向け 講師ガイドブック
合わせて読みたい
2023年3月に内閣府が発表した調査によると、15~64歳の引…
今や2人の1人がかかるといわれる「がん」。かつてがんは不治の病…
高度情報化社会の現代では、スマホやIoT(Internet o…
他の記事をみる



















業務外の講師への取次は対応しておりません。