
従業員を雇う際に安全衛生教育を実施することは、企業にとっての義務です。
この記事では、その理由や背景などを解説します。また、業種別や対象者別にどのような内容を盛り込む必要があるのかや、効果的な実施方法についても紹介します。
雇入れ時の安全衛生教育とは
企業が従業員を新たに雇う際には、安全衛生教育を実施する必要があります。実際にあった過去の違反事例を紹介するとともに、その理由について説明します。
安全衛生教育の法的背景:安全衛生法第59条
安全衛生法は第59条において、「労働者を雇入れたときは、該当労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない」と定めています。
つまり、すべての企業にとって、雇入れ時の安全衛生教育は法的な義務と明示されています。教育は従業員が安全に業務開始し、遂行するための大切な取り組みです。企業は、従業員へ教育を受ける場を提供することによって、労働災害の予防と安全への責任を果たさなければなりません。
新規就業者が安全に作業するために必要
企業から新規就業者に対し、安全衛生について教育することで、本人が作業時に「どのようなことに気をつければ良いか」を理解できるようになります。職場に潜む危険を事前に察知し、回避できるようになるでしょう。
労災を防止するのはもちろんのこと、従業員が安心して働きつづける環境を提供するためにも、安全衛生教育は重要な役割を果たします。
統計的背景
福岡労働局・八女労働基準監督の2020年の調査によると、管内で生じた労災において、経験年数1年以下の労働者が被災する労災の件数は全体の約3割を占めました。経験が少ない人は、経験のある人たちよりも明らかに多い傾向にあることがわかります。
さらに厚生労働省の2018年の調査では、「29歳以下」や「30〜39歳」などの区切りで年齢層別に見ても、「すべての年代において、経験1年未満の人のほうが被災する確率が高い」という事実が浮き彫りとなっています。
現場で経験の浅い人が、安全に対する知識が乏しいまま業務にあたっている状況が推測されます。こうした統計的背景からも、雇入れ時には安全衛生教育が必須であることは明らかです。
過去の違反事例
実例を紹介しましょう。過去には、サファリパークで、獣舎内で従業員がトラに襲われ負傷する労災が発生しました。また別の建設現場では、当日から働き始め、内装材の撤去に従事していた労働者が、建物の2階から墜落し負傷するという事案も発生しています。
これら2つの事案に共通しているのは、企業が雇入れ時の安全衛生教育を怠ったまま本人に作業を担当させていたという点です。法令に基づき、前者は会社と取締役が、後者は会社と現場責任者が書類送検されました。
さらに雇入れ時の安全衛生教育を怠った企業には、50万円以下の罰金が科せられる可能性もあります。
雇入れ時安全衛生教育の対象者
この章では、どのような内容の安全衛生教育を実施すれば良いか、業種別に具体的なポイントを紹介します。
製造業・建設業を含むすべての企業の新卒・中途入社の労働者
雇入れ時の安全衛生教育は、製造業・建設業のみならず、すべての企業の新卒・中途入社の従業員が対象です。
具体的な内容としては、以下のようなものが挙げられます。
- 機械や材料の危険性や有害性、取り扱い方法に関する内容
- 作業開始時の点検に関すること
- 業務に関して発生する恐れのある傷害の原因や予防法
また、中途入社の場合にも基本的には、教育を実施する必要があります(前職などの経験によっては省略可なケースあり)。
事務職・営業職などのオフィスワーカー
事務職や営業職などのオフィスワーカーへは、オフィス内で起こりうる事故のリスクを中心に注意喚起します。
例えば、非常口や避難経路の確認、電気・ガス設備などの取り扱い方を組み込むと良いでしょう。さらに社内の安全衛生管理体制について事前に周知しておくと、働く人にも安心です。
「電球を替えようとオフィスチェアの上に立ったところ、転落しかけてヒヤリ」などの「ヒヤリ・ハット事例」を加えることも効果的です。
外国人労働者
 雇用形態に関わらず外国人労働者に対しても、新規就業時には速やかに安全衛生教育を実施しなければなりません。
雇用形態に関わらず外国人労働者に対しても、新規就業時には速やかに安全衛生教育を実施しなければなりません。
対象者の母国語を使用し、視聴覚教材を用いるなど、本人が理解しやすい方法を事前に用意することが重要です。
厚生労働省やハローワーク・民間企業などが提供している、外国人対象教育の支援やサービスを利用すると良いでしょう。
派遣労働者
派遣労働者を対象とした安全衛生教育は、派遣元が対象者を雇入れたタイミングで実施する必要があります。
一方で、派遣先で新たに「法令で定められている危険・有害な業務に従事する」際や、そうした業務へ「作業内容を変更する場合」は、派遣先に教育責任があります(ただしこれは「雇入れ時教育」ではなく「特別教育」と「作業変更時安全衛生教育」に該当)。
また、派遣元と派遣先との連携や情報共有を徹底し、本人に必要な教育に漏れがない状況にしておかなければなりません。
再雇用などの高年齢労働者
さまざまな企業において、今後ますます高年齢の労働者が増えると予測されています。
高年齢の従業員に対しては、身体機能の低下によって高まるリスクなどを中心にレクチャーします。危険予知トレーニングや、転倒・腰痛予防に関する教育などを実施するとよいでしょう。
また本人だけでなく、高年齢労働者は若い従業員とは異なる注意点があることを、直属の上司や管理監督者も理解しておかなければなりません。
雇入れ時安全衛生教育の進め方
この章では、雇入れ時安全衛生教育はどのような流れで実施すればよいのかを、具体的な内容も併せて解説します。
基礎的な安全衛生についてのオリエンテーション
まずは、労災や職業疾病(いわゆる「職業病」)を防ぐため、安全衛生についての基礎知識を身につけてもらう必要があります。そこでオリエンテーションの機会を設け、例えば以下のような事項を伝えます。
- 職場のリスクアセスメント(作業中に生じる危険性や有害性を特定・評価し、そのリスクを減らすための活動)
- 安全装置利用や保護具着用の重要性
- 従業員自身による健康保持 など
安全衛生に関わる職場ルールの共有・確認
次に、安全衛生に関わる職場のルールを共有します。例えば、所定労働時間や服装規定の確認のほか、勤務拠点の防災体制や安全衛生保護具の着用ルールについても、事前に周知徹底しておく必要があります。
地震などの自然災害が発生した時の、避難場所や経路、緊急連絡先などもこれに含めます。
また、労災事故が発生した際の報告先や指示連絡系統、現場でどのような手順で対処するかなども盛り込むと良いでしょう。
職場全体の危険箇所・設備説明
さらに、職場内では特にどのような箇所に気をつければ良いかや、どの設備に注意が必要かなどを詳しく説明します。
その際、口頭や資料・図面で伝えるだけでなく、実際に対象者に現場を見てもらいます。危険箇所を自身の目で確認したり、実際に設備を作動させてみたりして、実践しながら伝えるのが効果的です。
業種別にみる雇入れ時安全衛生教育のポイント・注意点
続いて、雇入れ時安全衛生教育のポイントや注意点などについて、業種別に解説していきます。
建設業
建設業においては、高所からの墜落・転落事故、重機などへのはさまれ・巻き込まれ、解体作業中や資材の破壊・倒壊による下敷きなどが多く発生しています。
教育プログラムの中に、過去の事故事例と、それらの事例から得られた教訓や具体的な対策方法を盛り込むことが重要です。
また健康面では、長時間労働による脳・心臓疾患、ストレス過多による精神疾患なども多いと報告されています。健康面での労災リスクも含め、健康管理の知識や相談先などをしっかり伝えておくと良いでしょう。
製造業
製造業も、建設業に次いで労災の発生が多い業種です。
労働者全体の傾向と同様、経験年数が浅い人が被災する可能性が高い傾向があります。また、製造業全体の労災の中では、金属製品や化学工業のほか、食品製造が高い比率を占める業種であるのが特徴です。
未熟練労働者(経験3年未満)に対しては特に、機械へのはさまれ・巻き込まれや転倒などへの注意喚起が重要です。
運送業・ドライバー
 運送業では、荷役作業を行う際の墜落・転落、フォークリフトやクレーンなどの運搬機械による事故が多発しています。またドライバーには、長時間運転による腰痛や、昼夜不規則な勤務による健康問題も懸念されます。
運送業では、荷役作業を行う際の墜落・転落、フォークリフトやクレーンなどの運搬機械による事故が多発しています。またドライバーには、長時間運転による腰痛や、昼夜不規則な勤務による健康問題も懸念されます。
厚生労働省が公表している「荷役作業安全ガイドライン」の活用や、乗務前の対面健康チェックが有効です。本人が記入する健康管理ノートで日々の状況を把握すると、より安心でしょう。
飲食業・小売業
飲食や小売業の現場では、従業員にとって安全でない状況を解消し、リスクとなる行動を防ぐことが大切です。
不安全な状況は、整理整頓、清掃・清潔の徹底などで改善できます。また保護手袋の着用や、脚立の正しい使用方法などについては漏れなくしっかりと伝えます。ちょっとした油断によって生じる危険についてもレクチャーしておくと良いでしょう。
介護施設
介護施設においては、介助に伴う腰痛や転倒が多く発生しています。よって、介助者の身体的負担軽減が重要です。介助に伴う腰痛・転倒を防ぐため、用具の正しい使用や、身体への負担が少ない介助方法を伝えましょう。
また慢性的な人手不足などによってストレスが高い業種でもあり、それが労災リスクにもつながります。安全衛生の面からも、従業員自身の心身の健康配慮について注意を払う必要があります。
雇入れ時安全衛生教育の課題と解決のヒント
最後に、雇入れ時安全衛生教育について、多くの企業が今抱えている課題を確認しておきましょう。さらにその解決策について解説します。
雇入れ時安全衛生教育の課題
厚生労働省の2023年度「労働安全衛生調査」によると、雇入れ時安全衛生教育を実施している事業所の割合は56.1%に留まりました。つまり4割以上の事業所が、実態として「実施していない」という結果です。
義務化されているにもかかわらず、多くの職場で教育が形骸化している恐れがあります。また別の機関の報告によると「教育内容のマンネリ化」を課題とする企業が多いのも実情です。
外部講師活用のメリット
雇入れ時安全衛生教育の形骸化・マンネリ化を防ぐため、外部講師による研修や講習の場を活用してみてはいかがでしょうか。
さまざまな知見を持つ専門家による安全衛生講習は、従業員に対して常に最新の情報を盛り込めるだけでなく、より自社の目的に合うプログラムを提供できる点からもおすすめです。
SBがおすすめするプロによる職場の安全衛生教育
システムブレーンには、評価やリピート率の高いプロフェッショナルが講師として数多く在籍しています。ヒューマンエラー防止に特化したプログラムや、現場監督経験のある講師による講義など、自社の状況に即した課題解決に向けて、内容をカスタマイズできます。
合わせて読みたい
ビジネスでもお天気の話題は必要不可欠ですが、ゲリラ豪雨、猛暑日…
企業にとって「安全」は最重要課題です。当然ながら、各企業様で様…
職場の安全教育はマンネリ化していませんか?テーマや内容がいつも…
ここまで、企業に義務付けられた雇入れ時の安全衛生教育について、その重要性や業種別に盛り込むべき教育内容などについて解説してきました。労働災害ゼロを徹底するためにも、自社独自の教育に加えて、専門家による講習プランの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
あわせて読みたい
建設業や製造業などはもちろん、すべての業種において従業員が安全に、安心して働けるよう、安全衛生の考え方が重要です。本記事では、安全衛生の内容や目的、関連する法律や具体例について、わかりやすく解説します。
建設業や製造業などはもちろん、すべての業種において従業員が安全に、安心して働けるよう、安全衛生の考え方が重要です。本記事では、安全衛生の内容や目的、関連する法律や具体例について、わかりやすく解説します。
ルール不遵守・リスク認識不足による人身事故 安全大会の事例をご…
他の記事をみる








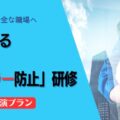
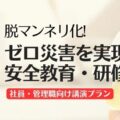












業務外の講師への取次は対応しておりません。