
従業員に安全に業務を遂行してもらうために、安全衛生教育は必要不可欠です。教育の一環として従業員の前でスピーチや講話を担当する際、毎回ネタ探しに困っている人も多いのではないでしょうか。
この記事では、安全衛生に関するネタの選び方や、季節ごとのテーマ例、面白い講話のヒントなどをご紹介します。
安全衛生講話の目的
安全衛生講話の目的は、働く人の命と健康を守るために、「気づき」と「行動の変化」を促すことです。単なる形式的な行事ではなく、現場での事故や病気を未然に防ぐための“きっかけづくり”として非常に重要です。
以下に、具体的な目的をわかりやすく整理してお伝えします。
① 労働災害・健康障害の防止
安全衛生講話の第一の目的は、現場で起こりうる事故や病気を未然に防ぐことです。転倒や挟まれ、熱中症、過重労働など、あらゆるリスクに対して「自分にも起こりうる」と認識してもらい、日々の業務での注意や行動を促すきっかけをつくります。特に、過去の事故例や身近なヒヤリ・ハット事例を共有することで、具体的なイメージを持たせ、危機感を高める効果が期待できます。
② 安全意識の向上と行動の変化
日々の業務に慣れてくると、安全への意識が薄れてしまいがちです。安全衛生講話は、その「慣れ」による油断を防ぎ、改めて危険への注意やルール順守の大切さを再認識してもらう機会です。また、「知っている」だけでなく「実際に行動に移す」ことが重要であり、講話を通じて小さな行動の見直しにつながることが期待されます。聞くだけで終わらず、自分ごととして考える姿勢を育むことが目的です。
③ 情報共有と職場の一体感づくり
安全衛生講話は、現場の作業員が知っておくべき最新の法改正や制度変更を周知する場としても重要です。例えば、2025年6月からは熱中症対策が企業にとって法的義務となり、早期発見体制の整備や重症化を防ぐ対応策が求められます。こうした情報を講話で共有することで、企業と従業員が同じ意識で対策に取り組む土台ができます。また、「安全は一人では守れない」という共通認識のもと、チーム全体で危険に気づき、声をかけ合える職場づくりにもつながります。
合わせて読みたい
夏の労働災害の原因として上位にあるのが熱中症です。特に7~8月…
建設業や製造業などはもちろん、すべての業種において従業員が安全に、安心して働けるよう、安全衛生の考え方が重要です。本記事では、安全衛生の内容や目的、関連する法律や具体例について、わかりやすく解説します。
建設業や製造業などはもちろん、すべての業種において従業員が安全に、安心して働けるよう、安全衛生の考え方が重要です。本記事では、安全衛生の内容や目的、関連する法律や具体例について、わかりやすく解説します。
スピーチのネタを選ぶ・作る際のポイント
では、安全衛生スピーチのネタの選定や、内容の構成はどのようにすれば良いのでしょうか。ここでは6つのポイントを説明します。
1.スピーチの目的を明確にする
まず最初に「なぜその話をするのか?」を考えましょう。
例えば:
- 事故を防止したい(注意喚起)
- 法改正など新しい情報を共有したい
- 危機意識を高めたい
- 身近な事例を通して行動を変えたい
この目的がブレないように、ネタや構成を組み立てると説得力が増します。
2. “現場に直結するテーマ”を選ぶ
スピーチの内容が、実際の業務や日常とどれだけ関係があるかが重要です。以下のようなテーマは現場でも関心を持たれやすいです。
- 熱中症・転倒・腰痛など、季節や作業に応じたリスク
- ヒヤリ・ハット体験(軽微な事故が重大災害に発展する例)
- 交通安全(通勤災害対策など)
- 労働災害の具体的な事例(他社の事故例を紹介して教訓に)
現場で起こりうる「あるある」を切り口にしましょう。
3.ネタの構成は「起→承→転→結」で
スピーチの流れが整っていると、聞き手も理解しやすくなります。
例えば、熱中症対策をテーマにした場合は、以下の通りとなります。
- 起(導入):「最近暑くなってきましたね。去年、隣の現場で起きた熱中症事故をご存知ですか?」
- 承(現状・事実):「実は、年間30人以上が熱中症で命を落としており…」
- 転(問題提起・対策):「でも、ある対策をしていた現場では発症者がゼロだったんです」
- 結(まとめ・呼びかけ):「今年も、声かけとこまめな水分補給を徹底しましょう!」
4.具体例・数字・体験談を入れる
抽象的な話よりも、「数字・事例・体験談」があると聞き手に刺さります。
「◯◯県では今年◯人が熱中症で搬送されました」
「私の知人が、現場で倒れて…」
など、“リアルさ”を演出することで伝わりやすくなります。
5.聞き手の“自分ごと”にする
「それって自分にも起こり得るかも」と感じてもらうことが、行動変容につながります。
例えば、
「昨日寝不足だった方、今日の作業に注意が必要です」
「ちょっとの油断が事故につながります。私も◯年前に…」
聞き手が「他人事」ではなく「自分事」として受け止められる工夫をしましょう。
6.ポジティブに締めくくる
最後は、以下の通り、「明るく・前向きに」まとめると印象が良くなります。
「今年の夏は、全員で熱中症ゼロを目指しましょう!」
「安全は“みんなで守るチームプレー”です。一緒に意識していきましょう!」
すぐに使える定番の安全衛生スピーチネタ10選
続いて、安全衛生のスピーチを依頼された際に、すぐに使える定番のネタを紹介します。
①ヒューマンエラー防止
人は誰でもエラーを起こす可能性があります。しかしエラー自体が「事故の原因」なのではありません。人のエラー行動も「結果」であり、その裏には必ず原因があります。この観点がないと、人を替えても同様の事故を再発させる恐れがあります。
なぜ人為ミスが起きるのか、どのようにすれば防ぐことができるのかなど、近年起こった重大事故などの事例を踏まえながら伝えます。
②労働災害やヒヤリハットの事例
労災は最悪の場合、人命が奪われたり、その後の生活にも支障を来たしたりする深刻な問題です。聞く人に、机上の空論ではなく、自分事と感じてもらうことが大切です。
実際に起こった事故でどのような被害があり、当事者やその家族などにどのような影響があったかなどは、自分と重ねやすいでしょう。過去に同じ職場で起こった「ヒヤリハット」の実例なども、光景を思い浮かべやすく、効果の高い話題の1つです。
③季節に応じた体調管理への注意喚起
季節に応じた体調管理の方法や、注意すべきポイントを伝えるのも有効です。なぜなら、従業員が安定的に仕事を続けていくには、自身で心身の健康状態をきちんと把握し、維持していることが前提だからです。
具体的には、夏なら食中毒や熱中症予防、秋から冬にかけてはインフルエンザ対策などがあります。
この記事の後半では、1年12カ月分のネタの例を紹介しています。
④労働災害統計データの紹介
厚生労働省が発表している労働災害統計のデータを用いて伝えるのも一案です。例年、最新データとして前年の集計結果が5月頃に発表されます。
自社の状況に応じて、参考になる業種や原因などの数値を選ぶと良いでしょう。
参照:厚生労働省「職場のあんぜんサイト」労働災害統計(令和5年)
⑤クイズ形式で学ぶ安全衛生
スピーカーが一方的に話をしているだけでは、聞き手の注意を引くことができません。参加型のスピーチにするのもおすすめです。
クイズ形式を取り入れると、楽しみながら知識を学べます。挙手などで反応を見ながら話を展開する、安全衛生スピーチ向けクイズを掲載した書籍なども発売されています。参考にしてみましょう。
⑥ストレッチ・体操
特に身体を使った作業がある職場の場合、急に業務を始めると思わぬ怪我につながるケースがあります。ストレッチや体操など、身体を動かしほぐす機会を設けることで、怪我防止の役割を果たすでしょう。
また、デスクワークの従業員にも、朝礼の時間などを活用してストレッチを導入している企業もあります。
⑦安全道具・装備の正しい使い方
 安全道具や装備の正しい使い方について改めて知識を共有し、互いに再確認するのも効果的です。
安全道具や装備の正しい使い方について改めて知識を共有し、互いに再確認するのも効果的です。
例えば「保護メガネは、使用する前にキズやヒビがないかを確認する」といった最も初歩的な内容でも構いません。「こんな基礎的なことは誰でも知っているはず」と決めつけるのではなく、スピーチなどの機会を通じてこまめに言葉にし、伝えることに意義があります。
⑧メンタルヘルス・健康管理
従業員のメンタルを含む健康管理は、企業で把握・管理できる範囲には限界があります。よってセルフケアが重要です。
メンタル面では、ストレスの原因や現在の負荷状況、対処法を知っている人ほど安定したパフォーマンスが発揮できます。身体面でも、生活習慣改善や健康診断の積極的な受診など、スピーチで推奨できることはいくつもあります。
➈交通安全
運送業や営業職など、日常的に車の運転を伴う職場の場合、交通安全の話題も有効です。
例えば、悪天候の日には視界不良で歩行者を見落としがちであることや、雨の多い時期に車が浸水した時の対処法などを話します。「わかったつもり」になりがちな事項を対面でしっかり伝えることで、油断による事故やトラブルを防ぎます。
⑩実際のリスクアセスメント事例
「リスクアセスメント」は、企業の安全衛生教育の中でも非常に重要な取り組みです。リスクアセスメントとは、「職場に潜む危険性を特定し、その原因や影響を分析し、適切な対策を講じるプロセスのこと」を指します。
職場のリスクアセスメント事例はwebなどで多く公開されており、厚生労働省のweb サイトからも、実施事例集や関連資料・教材などの資料が閲覧できます。
安全衛生スピーチ 月ごとのネタの例
続いて、安全スピーチで使える1年・12ヵ月分のネタについて、月ごとに紹介していきます。
4月:新年度
新年度は多くの企業で新入社員を迎える時期でもあります。上司が部下のメンタルケアを行う「ラインケア」の基礎知識などの情報を提供すると良いでしょう。
また気温が高くなってくることから、居眠り運転防止を呼びかける企業も多いです。運転中に眠気を感じたらすぐに車を停めることや、短時間仮眠の効果やリフレッシュの方法などを伝えます。
5月:メンタルケア
大型連休明けは、心身の不調を訴える「五月病」に気をつけたい時期です。本人の自覚症状だけでなく、周囲が気づけるサインなどを共有しておくのも有効です。
心理学に基づくリラクゼーション技法など、自分でできるメンタルケアについて伝えても良いでしょう。
6月:長時間労働・職業疾病対策
業務に慣れ、日が長くなるこの時期は、労働時間も延びがちです。長時間労働が引き起こす身体の不調は多々あります。ずっと同じ姿勢を取り続けることも、職業疾病につながります。
睡眠の質の低下や肩こり・腰痛などはその代表です。勤務中に適宜休憩を取り入れ、体操やストレッチを行うことで改善できる可能性があります。
7月:全国安全週間
毎年7月1日から7日までは「全国安全週間」です。これにちなんで、7月は安全衛生活動の目的を再確認し、従業員一人ひとりの意識を高めましょう。
職場の危険な箇所の周知や指差呼称(声に出しての安全確認)を徹底したり、全国安全週間の歴代スローガンを引き合いに出して自社の過去の事例を紹介したりするのも効果的です。
8月:熱中症予防
毎年、夏の労働災害の原因ランキングの上位に入るのが熱中症です。2025年6月からは、企業に対して熱中症対策の実施が法的に義務化され、屋外作業はもちろん、屋内業務においても適切な予防措置が求められるようになりました。
熱中症の原因や症状などの基本的な知識に加え、水分補給やこまめな休憩の重要性、早期発見の仕組みづくりなど、具体的な対策を話題にしましょう。各現場の業務環境や作業特性に応じた伝え方を意識することが、実効性ある対策につながります。
9月:防災の日
 9月1日は防災の日です。スピーチを通じて、防災意識を再認識してもらう好機です。
9月1日は防災の日です。スピーチを通じて、防災意識を再認識してもらう好機です。
例えば、自然災害が発生した際、職場での身の安全を確保する方法や、避難場所・避難経路の再確認などがおすすめです。自社の防災への取り組みについても、しっかり周知しておきましょう。
10月:交通事故対策
日の入りが早くなるこの季節は、交通事故の件数が急激に増える時期でもあります。適切な車間距離、横断歩道周辺での正しいルールなど、基本的な事項を徹底するのも有意義です。
運転中に見落としがちな、右折先の歩行者に注意するなど、死角や夜間の注意点を改めて知らせると良いでしょう。
11月:感染症予防
インフルエンザやノロウイルスといった感染症は、空気が乾燥し気温も低下するこの時期から、流行し始めます。
まずは感染経路や症状の見分け方、手洗いなどの対策が基本です。疾病別の予防法、例えばインフルエンザであれば部屋の加湿や人ごみの回避、ノロウイルスであれば食品の加熱や器具の消毒などを紹介すると、すぐに役立つでしょう。
12月:暖房器具安全利用
暖房器具の使用機会が増える冬。メンテナンスを怠って不適切な方法で使用すると、思わぬトラブルにつながります。
フィルターの掃除や電気コードの配線確認など、聞いた日から即実践できる内容を盛り込むのがおすすめです。
1月:アルコールとの付き合い方
アルコールは、リラックス効果をもたらしコミュニケーションの場でも役立つ一方で、過度な飲酒はさまざまな問題につながります。特に業務で車の運転や危険な機械・装置に関わる人は油断厳禁です。
適切な飲酒量やアルコールによる健康被害などを周知し、事故やトラブルを防止します。
2月:路面凍結
冬の路面凍結には注意が必要です。歩行時の転倒や、車のスリップなどに警戒しなくてはなりません。
夜間の照明点灯、冬用タイヤへの交換、滑りにくい作業靴の着用のほか、「ながら歩き」の禁止など、注意すべきポイントについて盛り込みましょう。
3月:花粉症対策
4〜5割の人が花粉症といわれ、毎年花粉の飛散量が多くなる3月に関心が高まる話題です。マスクやメガネの着用、うがいや洗顔などといった基本的な対策方法のほか、衣服についた花粉を払うなど、室内にも持ち込まないための工夫も大切です。
面白い安全衛生スピーチのアイディア
スピーカーがただ一方的に話をしていては、なかなか相手には伝わりません。聞き手を引きつけられる面白い安全衛生スピーチのアイディアをご紹介します。
①安全衛生標語の紹介
厚生労働省や中央労働災害防止協会、中小建設業特別教育協会などが多くの安全衛生標語を発表しています。
例えば「マンネリ化 あなたの心が 危険物」など、思わずクスッとなってしまうような標語を紹介しつつ、その表現を活用して注意点を伝えるのも良いでしょう。
②社内アンケートの活用
社内や業界内の状況など、身近な話題を取り入れることでより関心を引くことができます。
社内アンケートを実施し、その結果を事実として盛り込むとより効果的です。「職場内で危険を感じている場所はどこか」や、「そこでどのような対策が取れるか」などを、聞き手も一緒になって考えられるのでおすすめです。
安全衛生講話ネタの探し方
当番制などで毎回のスピーチネタ探しに行き詰まることもあるでしょう。最後に、ネタ探しの参考になる2つのヒントを紹介します。
同業者や業界団体の事例を調査する
話す内容は、社内や業務の実情に合わせるのが鉄則です。従業員にとって、同業他社や業界団体が実際にどのような取り組みを行っているかを伝えるのも有益です。
webサイトや公開資料などから、安全衛生スピーチに使える事例や調査結果の発見につながることもあるでしょう。
書籍やオンライン資料を活用する
安全衛生講話に関しては、さまざまな書籍やwebサイトが存在します。それらの中には、テーマ案やスピーチの本文がそのまま提供されているものもあります。
このほか、同業者や業界団体同様、公的機関がオンラインで発表している資料なども役立ちます。さまざまな資料をチェックすれば、講話のネタが多く見つかるでしょう。
安全衛生講話は、従業員に正しい知識を身につけてもらうこと、職場の環境改善につなげることが目的です。そのためには、聞く人の興味を引くようなトピックや業種・職場環境に応じたテーマ、季節に合う話題などを盛り込みながら内容を設定すると良いでしょう。
あわせて読みたい
建設業や製造業などはもちろん、すべての業種において従業員が安全に、安心して働けるよう、安全衛生の考え方が重要です。本記事では、安全衛生の内容や目的、関連する法律や具体例について、わかりやすく解説します。
建設業や製造業などはもちろん、すべての業種において従業員が安全に、安心して働けるよう、安全衛生の考え方が重要です。本記事では、安全衛生の内容や目的、関連する法律や具体例について、わかりやすく解説します。
建設業や製造業などはもちろん、すべての業種において従業員が安全に、安心して働けるよう、安全衛生の考え方が重要です。本記事では、安全衛生の内容や目的、関連する法律や具体例について、わかりやすく解説します。
他の記事をみる













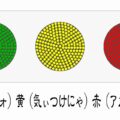








業務外の講師への取次は対応しておりません。