
文部科学省の調査によると、2023年度の小中学校における不登校児童生徒数は約34万6千人に達し、過去最多を更新しました。特に小学生の不登校が増加傾向にあり、低学年から学校生活に適応できず孤立する子どもが目立ちます。
不登校はもはや家庭だけで抱えるべき課題ではなく、地域社会全体で理解と支援が求められる重要な問題です。こうした現状をふまえ、不登校の当事者や支援者が自らの体験や想いを語る講演プランをご紹介します。
不登校についてみんなで考える時間を設けてみませんか?
■目次
- 南雲明彦 『不登校とどう向き合ってきたか ~僕がボクであるために~』
- 家田荘子 『ティーンからのメッセージ~知ってもらいたい。子どもたちのこと~』
- 白井智子 『誰もとりこぼさない教育を目指して ~不登校・ひきこもり・発達障害の子どもの支援を通じて~』
- アグネス・チャン 『未来を担う子どもを育てる ~心を豊かにする教育とは~』
- 玉田玉秀斎 『人権先進国 スウェーデンで学んだ講談師が語る~違いがあるからおもしろい 道は一本じゃない~ 』
- 宮本延春 『オール1の落ちこぼれ、教師になる ~いじめ、引きこもり、天涯孤独の絶望を乗り越えて~』
- 遠藤剛志 『私と出会った子どもたち ~不登校・引きこもりからの脱出~』
- なだぎ武 『「サナギ」講演会 ~いじめに負けず、明るい未来をつかみ取る方法~』
南雲明彦 なぐもあきひこ
明蓬館(めいほうかん)高等学校
共育コーディネーター
不登校とどう向き合ってきたか
~僕がボクであるために~

21歳の時に学習障害の1つであるディスレクシアであることが判明した南雲明彦さん。10代後半に精神障害を発症。高校は、転・編入を繰り返し、不登校、引きこもりを経験したと言います。現在は、明蓬館高等学校共育コーディネーターとして活動する傍ら、発達障害で悩む子ども達や保護者、教育関係者の方々に講演を行っています。「不登校時代、得たものもあったが、失ったものの方が多かった」と語る南雲さんが、これまでの道のりを振り返りながら、保護者や教育者・社会が不登校・引きこもり児童・生徒に対してどう向き合っていくべきなのかを一緒に考えていきます。
|
講師ジャンル
|
教育・青少年育成、 人権・平和、 福祉・介護 |
|---|
主催者様からの声
机上論でない実体験に基づいたお話は多くの気づきと理解を得ることことができました。また、障がいを持たない子どもをもつ保護者や教育関係者にとっても十分価値のあるお話でした。
家田荘子 いえだしょうこ
作家
僧侶(高野山本山布教師・大僧都)
ティーンからのメッセージ
~知ってもらいたい。子どもたちのこと~

女子少年院の榛名女子学園に一年間を通して取材し、DV、ひきこもり、自殺、摂食障害、リストカット、薬物、犯罪などを経験した子どもたちと向き合ってきた作家の家田荘子さん。入所者やその家族を取材する中で一番大切なのは「家族」であることを強く感じたと言います。本講演では、これまでの取材経験をもとに、同じ時代を生きる違う土地の子どもたちの実態を伝え、私たち周囲の大人が問題を抱える子どもたちにどんな手を差し伸べられるかを考えていきます。
|
講師ジャンル
|
文化・教養、 人権・平和、 教育・青少年育成、 コミュニケーション、 ライフプラン、 福祉・介護 |
|---|
主催者様からの声
開催目的をしっかりくみ取って頂いた内容で、多くの気づきと心のこもったメッセージを頂き、素晴らしい大会になりました
白井智子 しらいともこ
特定非営利活動法人 新公益連盟代表理事
誰もとりこぼさない教育を目指して
~不登校・ひきこもり・発達障害の子どもの支援を通じて~

講師の白井智子さんは、国による不登校の子どもたちの支援がほとんどなかった20年前、沖縄に不登校の子どもたちが通うフリースクールを立ち上げました。以来、何千人もの子どもたちが元気と自信を取り戻し、社会で活躍していく中、2017年に初めて国による不登校の子どもを支援する法律『教育機会確保法』が制定。この法律は、白井さんの教育モデルも参考にしており、そのときの経験談を、子どもや親のリアルな声をまじえて語ります。ひきこもりや不登校の子供たちに対して、地域の支援策になるヒントが満載です。
|
講師ジャンル
|
教育・青少年育成 |
|---|
主催者様からの声
白井さんが考案した支援システムがとても画期的であり、今後、私たちの地域での取り組みでも活用できそうです。とてもためになる情報をいただけました。
アグネス・チャン あぐねすちゃん
歌手、エッセイスト、教育学博士
未来を担う子どもを育てる
~心を豊かにする教育とは~

「いじめ」「ひきこもり」「不登校」「ニート」など言葉は変わっても青少年の問題は、いつの時代も社会の大きな課題となっています。3人の子の母親として、また教育学博士として「教育の基本は家庭にある」という信念を持っているアグネス・チャンさんは、“自分自身をよく知り、自分に誇りの持てる子どもに育てる”ことの必要性を強調しています。実体験に基づく独特の子育て論だけでなく、心理学、教育学などあらゆる視点から子どもを取りまく環境の改善を訴え、教育改革、親と子の意識改革などについても言及します。
|
講師ジャンル
|
教育・青少年育成、 文化・教養、 人権・平和、 環境問題、 健康、 福祉・介護、 国際化・グローバル |
|---|
主催者様からの声
非常にうまくいきました。講演も好評で参加者の方々も喜んでおられました。
玉田玉秀斎 たまだぎょくしゅうさい
講談師
人権先進国 スウェーデンで学んだ講談師が語る
~違いがあるからおもしろい 道は一本じゃない~

講師の玉田玉秀斎さんは、小中学校でいじめに遭うものの、母親の支えもあり、一念発起して高校でスウェーデンに留学します。言葉の通じない外国で家族と離れての暮らしに、孤独や失意を経験し、家出した先でスウェーデン人にかけられた言葉が「違いがある方がおもしろい」ということ。「イジメられても、家出をしても、自殺がしたくなっても大丈夫。私たち人間は、決して強い人ばかりじゃありません。人が歩める道は1本だけではありません」と語る玉田玉さんの力強いエールを受け取ってください。
|
講師ジャンル
|
人権・平和、 国際化・グローバル |
|---|
主催者様からの声
親しみやすい講師の方で、講演前の打ち合わせも遠慮なくさせていただき、スムースに開演できました。内容も分かりやすく、ポイントもきちんと話され、受講者からも「よかった。」との評価をいただきました。
宮本延春 みやもとまさはる
エッセイスト、元 高校教諭、作家
オール1の落ちこぼれ、教師になる
~いじめ、引きこもり、天涯孤独の絶望を乗り越えて~

元高校教諭で作家の宮本延春氏が、自身の壮絶な半生をもとに、いじめや不登校、家庭環境の困難を乗り越えた経験を語ります。学習意欲を失った原因や、夢や目標を持つことの重要性を実体験から解説。子どもが発するSOSのサインを見逃さず、適切に支える方法や、学ぶ楽しさを伝える大切さを具体的に紹介します。自身が目標を見つけ、支えてくれる人と出会うことで人生を変えた経験をもとに、子どもを温かく支えるヒントを提供します。
|
講師ジャンル
|
教育・青少年育成、 文化・教養、 モチベーション、 安全管理・労働災害、 人権・平和、 男女共同参画 |
|---|
主催者様からの声
大変良い内容の講演であったとの感想を多数いただきました。聴講した中学生も共感している様子でした。この講演内容をもっと学校関係者にも聞かせたいとの意見がありました。
遠藤剛志 えんどうつよし
青少年育成団体 ANDANTE責任者
私と出会った子どもたち
~不登校・引きこもりからの脱出~

全寮制学校の教諭寮監や通信制高校サポート校の学校長を務めた経験を持つ、青少年育成団体ANDANTE責任者の遠藤剛志氏が、不登校・引きこもり・非行・鬱病など様々な問題を抱えた子どもたちと向き合ってきた実体験を語ります。信頼関係の構築を最優先に、子どもたちの不安や怒りを受け止めながら共に歩んできた経験を通じ、子どもたちが社会とつながるために必要な支援の在り方を提案します。大人や社会ができることを考える講演です。
|
講師ジャンル
|
人権・平和、 教育・青少年育成 |
|---|
主催者様からの声
遠藤剛志氏の講演では、不登校や引きこもりの子どもたちとの向き合い方について、実体験を交えた熱いメッセージが伝えられました。信頼関係の大切さを改めて実感し、参加者からも「子どもと本気で向き合いたい」との声が多く寄せられました。
なだぎ武 なだぎたけし
お笑いタレント 漫談家
「サナギ」講演会
~いじめに負けず、明るい未来をつかみ取る方法~

幼少期に壮絶ないじめを経験し、引きこもりや摂食障害を乗り越えたなだぎ武氏が、自身の体験をもとに「いじめを受けた人間の気持ち」「いじめを受けている子どものサイン」「立ち直る方法」について語ります。重いテーマながらも、明るくユーモアを交えて伝えることで、多くの方が前向きに考えるきっかけを得られる講演です。子どもから保護者、先生まで、いじめと向き合う全ての人に向けた内容となっています。
|
講師ジャンル
|
人権・平和 |
|---|
主催者様からの声
アンケート調査の結果、9割の方が、講演内容に満足されていた。講演に参加され、人権問題に関心を持たれ、何かしら行動しようと思った方が8割おられた。
合わせて読みたい
2023年3月に内閣府が発表した調査によると、15~64歳の引…
介護の問題、子育ての問題、それから防犯・防災においても地域の支…
2025年には、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、5人…
他の記事をみる
 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました 講師候補」から削除されました
講師候補」から削除されました









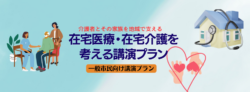








業務外の講師への取次は対応しておりません。