
近年、教育現場では「主体的・対話的で深い学び」が重視されるようになり、アクティブラーニングを取り入れた授業づくりが求められています。しかしながら、「実際にどのように授業に取り入れれば良いのか分からない」「教員の意識がバラバラで研修が進みにくい」といった悩みを持つ学校関係者も少なくありません。
本記事では、教職員研修を企画・運営する研修担当者の皆さまに向けて、アクティブラーニング研修のポイントと問題解決のヒントとなる研修プランをご紹介します。教員の意識改革と授業改善を同時に実現するためのヒントを得ていただければ幸いです。
そもそもアクティブラーニングとは?
 アクティブラーニングとは、「能動的学修」を意味し、学修者(児童・生徒・学生など)が受け身の姿勢ではなく、自ら積極的に学びに関わるよう設計された教授・学習法のことです。たとえば、グループワークやディベート、発見学習、問題解決型学習(PBL)、体験学習、調査学習などが含まれます。
アクティブラーニングとは、「能動的学修」を意味し、学修者(児童・生徒・学生など)が受け身の姿勢ではなく、自ら積極的に学びに関わるよう設計された教授・学習法のことです。たとえば、グループワークやディベート、発見学習、問題解決型学習(PBL)、体験学習、調査学習などが含まれます。
元々は、2012年に中央教育審議会答申(※)の中で、大学教育改革の一環として提唱された用語であり、その中でアクティブラーニングとは「教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称」としています。
当初は大学教育に焦点が当てられていましたが、現在では小・中・高校など初等中等教育にも導入が進んでおり、「主体的・対話的で深い学び」を実現する手段として注目を集めています。
その目的は、単なる知識の習得にとどまらず、認知的・倫理的・社会的能力、教養、知識、経験といった汎用的能力の育成にあります。これにより、学修者は自ら考え、他者と協働しながら学びを深める力を身につけていくことにあります。
つまり、アクティブラーニングとは、教員が一方的に教える授業ではなく、学修者が自ら関わり、学びをつくっていく学習方法なのです。
※「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて~生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ~(2012年答申)」
なぜ教職員研修でアクティブラーニングを扱うべきなのか?
近年、教育現場では「主体的・対話的で深い学び」を実現する手法として、アクティブラーニングの導入が進められています。2018年のリクルート進学総研のアクティブ・ラーニング調査によると、全国の全日制高校の90.4%がアクティブラーニング型授業を導入しており、学校全体で組織的に取り組んでいる高校は2014年の8.7%から2018年の29.3%と3.4倍ほど増加しています。
一方で、現場からは「うまくいかない」「続かない」「形だけで終わっている」といった声も少なくありません。実際、同調査では、58.6%の高校が「教員の指導スキルの向上」を課題として挙げています。
また、「アクティブラーニング失敗事例ハンドブック」(中部地域大学グループ・東海Aチーム、2014年)では、アクティブラーニングの失敗要因が「失敗原因マンダラ」として視覚化され、以下のような課題が浮き彫りになっています。
【主な失敗事例の要因】
- 目的喪失:「何のためにやるのか」が共有されておらず、活動が形骸化している
- 授業準備不足:アクティブラーニングの授業設計に必要な準備が足りず、即興で進めてしまう
- 教員の知識・スキルの不足:グループワークやディスカッションのファシリテーション方法がわからない。生徒の認知能力・思考力を引き出す指導力が弱い
- 教員間の価値観の違い:「今までの授業で十分」という意識が一部に残っている
こうした問題は、単に「教え方」を変えるだけでは解決できません。むしろ、教職員一人ひとりが「なぜアクティブラーニングが必要なのか」を理解し、自ら体験し、納得して実践できる状態を作ることが重要です。
研修の必要性
アクティブラーニングは、従来の一斉講義型の授業とは根本的に異なり、「学習者中心」「思考プロセスの重視」「他者との対話による内省」が中核にあります。したがって、授業を行う教員自身がその意味や方法を理解していない場合、単なる「グループワークをさせるだけ」の活動に終始してしまい、学習者にとっての意味ある学びにはつながりません。
そこで重要になるのが、教職員研修における「体験的理解」と「実践力の育成」です。
たとえば、ある中学校で導入されたアクティブラーニング研修では、教員自身がディスカッションや問題解決型学習を体験することで、「こういう視点で授業を見るのか」「生徒の主体性を引き出すとはこういうことか」という“気づき”を得ることができました。
このように、単なる座学の研修ではなく、教員自身が“学び手”として能動的に研修に関わることが、教育実践の転換につながるカギになります。
アクティブラーニング研修の目的
アクティブラーニング研修の目的は、単に「新しい授業手法を学ぶこと」ではありません。教職員が、これからの時代に求められる教育観を共有し、授業を質的に転換していく力を身につけることにあります。
主な目的は以下の通りです。
- 「主体的・対話的で深い学び」を理解し、実践に活かす
→ 学習指導要領の理念を、自らの授業改善に落とし込む力を育成。 - 受動的な授業からの脱却と授業改革の促進
→ 一方向型の授業から、学び手の思考を深める授業へと転換する視点を持つ - 学校内での授業観・評価観の共通化
→ 校内研修や協働的な授業づくりを支える基盤を整える - 教職員が「学び手」になる体験を通して視点を変える
→ 自分たちも学ぶ立場を体験することで、生徒の気持ちを理解し、授業改善への意欲が高まる
アクティブラーニング研修のメリット
 アクティブラーニング研修を導入することで、教員個人の授業力だけでなく、学校全体の教育力の底上げにもつながります。以下はその主なメリットです。
アクティブラーニング研修を導入することで、教員個人の授業力だけでなく、学校全体の教育力の底上げにもつながります。以下はその主なメリットです。
1. 授業の質が向上し、生徒の学びが深まる
ワークやディスカッションを通じて、教員が具体的なアクティブラーニング型の授業案を設計できるようになります。その結果、生徒がより主体的に授業へ参加するようになり、思考力・表現力・判断力の育成につながります。
2. 教員の授業に対する“意識改革”が進む
「なぜ変えるのか?」「どう変えるのか?」を学ぶことで、教員が授業づくりに対して前向きな姿勢になります。研修によって、受け身の実施ではなく、自ら考える力が身につきます。
3. 教員同士の対話が活性化し、協働的な風土が生まれる
研修の中でグループワークや模擬授業を行うことで、校内のつながりが強まり、チームで授業改善に取り組む雰囲気が醸成されます。
4. 校内研修の質向上にも貢献
アクティブラーニング研修で得た知見を活かして、次年度以降の校内研修や研究授業の設計がより実践的・継続的になります。
5. 外部評価にも対応しやすくなる
新しい学習指導要領や教育委員会の方針、学校評価などで求められる「授業改善」「カリキュラム・マネジメント」にも的確に対応できるようになります。
SBおすすめのアクティブラーニング研修プラン
ここでは、弊社が自信を持っておすすめする研修プランをご紹介します。アクティブラーニング導入前、導入後の課題解決のヒントとなるプランばかりです。
アクティブラーニングの実践
授業運営に活かすファシリテーション力
主体的に学ぶ力を育てるには、教員自身の授業運営の工夫が不可欠です。本研修では、松尾久美子氏(ファシリテーション研修の専門家)による、“楽しく学べる授業づくり”の視点から、アクティブラーニング実践に役立つファシリテーションスキルを習得します。生徒の主体性を引き出し、学びへの意欲を高める授業をともに考える機会となります。
たった一度の人生を変える勉強をしよう
正解のない時代に必要な学びとは何か。元民間校長で「人生の教科書作家」とも称される藤原和博氏が、探究型授業の視点と実践を伝えます。生徒が自ら「納得解」を導き出す力を育むために、教員が今こそ学び直すべき“新しい学び”の在り方を提案する研修です。
アクティブラーニング研修(仮)
英語音読教材『カラオケ!English』で日本eラーニングアワードを受賞した行正り香氏が、子どもたちの主体性を育むアクティブラーニングの実践を紹介。学習者の心を動かす「場づくり」や「仕掛け」の工夫を、生活や言語教育と結びつけて提案するクリエイティブな研修です。
家庭でできるアクティブ・ラーニング
生活の中で自分で考える力をつける
日常生活を“探究の場”に変える視点を、教育デザインラボ代表・石田勝紀氏が伝授。子どもが主体的に学び、自ら考える習慣を育てる家庭でのアクティブ・ラーニング実践法を学びます。地頭を育む生活ベースの学びが、学力向上と学習意欲の土台をつくります。
アクティブラーニング研修(仮)
河合塾講師・教育ライターとして活躍する朝倉浩之氏が、子どもが“学びを好きになる”ためのアクティブラーニングの工夫を紹介。生徒の好奇心を引き出し、自ら学ぶ姿勢を育む授業の秘訣を、受験指導の豊富な実践とともにお伝えします。
学校を見つめなおす
~子どものケア、先生の働き方、教育のあり方~
文部科学省や全国の教育委員会支援の経験をもつ教育研究家・妹尾昌俊氏が、授業改革・組織づくりに活かせるアクティブラーニングの考え方と実践を提案。問いかけやミニワークを交えた参加型研修を通じて、教職員が“自ら学び続ける組織”への第一歩を踏み出すきっかけを提供します。
個別指導塾の講師向け研修アクティブ・ラーニング入門~塾生の9割が成績アップする学習法~
All About学習・受験ガイドで活躍する伊藤敏雄氏が、生徒の9割が成績を伸ばす「間違い直し勉強法」や、塾で実践できるアクティブラーニングの基本を解説。説明中心から“生徒が自ら学ぶ”指導への転換をめざし、個別指導の現場で効果的な学習法を習得できます。
ICTを授業で、学校経営で活かす
ICTの導入はゴールではなく、学校を元気にする手段です。元校長であり実践家の玉置崇氏が、授業や学校経営にICTをどう活かせば教職員の働き方やチーム力が変わるのか、豊富な実例をもとに伝えます。“学校力”を高め、保護者や地域からの信頼を得るためのICT活用の第一歩となれる内容です。
アクティブラーニング研修(仮)
教育社会学者・内田良氏が、学校現場に潜む見えにくい“教育リスク”を題材に、アクティブラーニング型授業の設計と問いの立て方を考察。身近なテーマを通じて、生徒の主体性や対話力を引き出す授業づくりの視点を学びます。
AIに負けない創造的な子どもに育てるための秘訣
AI時代に必要なのは、検索力ではなく“即興力”と“創造性”です。演劇教育の第一人者・別役慎司氏が、即興演劇を活用したアクティブラーニング型授業の可能性と、子どもの表現力を引き出す手法を伝えます。
変化の激しい時代を生き抜く「自分で考え、動ける力」を育てる新しい教育のかたちを体験する研修です。
アクティブラーニング研修の内容例
アクティブラーニングを軸とした主な研修内容例を以下に5つご紹介します。
これらは学校現場の実情に即したテーマで、NITSの考え方(授業改善・チームでの協働・地域との連携など)を踏まえた内容となっています。
1. 「主体的・対話的で深い学び」を実現する授業デザイン研修
▶︎ 対象:すべての教員(特に若手〜中堅)
- 学習指導要領の背景にあるアクティブラーニングの意義を再確認
- 単元設計・授業構成における「問い」の立て方
- 観点別評価と学びの可視化を意識した授業改善
- ワーク:自教科の単元をもとにアクティブラーニング型授業を設計
2. 協働的な学びを支えるファシリテーション技術研修
▶︎ 対象:中堅〜リーダー層の教員
- 対話の質を高める問いかけ・傾聴・まとめのスキル
- 多様な意見を引き出し、まとめる進行技術
- ワーク:ミニ模擬授業とフィードバックによる実践力強化
- チームティーチングや校内研究にも応用可能
3. ICTを活用したアクティブラーニングの実践研修
▶︎ 対象:ICT導入に関心のある教員・情報担当
- GIGAスクール構想と学びの個別最適化との関連
- タブレット・Google Classroom・Jamboardなどの活用法
- ICTを使った「協働的な学び」「振り返り活動」実践例紹介
- 実習:オンライン・ハイブリッド授業におけるアクティブラーニングの組み立て
4. 学校全体でアクティブラーニングを推進する校内研修設計研修
▶︎ 対象:教務主任・管理職・研修担当者
- 校内研修を通じて「学び続ける組織文化」を形成する手法
- 校内の指導観・評価観の共有を促すファシリテート技術
- 年間研修計画の立て方と教員の巻き込み方
- ケーススタディ:ある学校の研修改革事例紹介
5. 地域課題とつながる探究型アクティブラーニング研修
▶︎ 対象:総合的な探究の時間やSDGs教育に関心のある教員
- 探究学習とアクティブラーニングの違いと共通点
- 地域との連携によるプロジェクト型学習(PBL)設計
- 「問い→調査→発表→ふりかえり」のステップ設計法
- 実践例:地域企業やNPOと連携した学習活動の紹介
アクティブラーニング研修開催時の注意点
アクティブラーニング研修を効果的に実施するためには、単にワークを取り入れるだけでなく、運営や設計の段階での工夫がとても重要です。以下に、研修担当者が押さえておくべき注意点を3つご紹介します。
1. 「なぜこの研修を行うのか」を明確に共有すること
教員の中には「また新しい手法を押し付けられるのか」と感じてしまう方もいます。そこで重要なのが、研修の目的や背景を冒頭でしっかり伝えることです。
「生徒の学びを深めるために授業をどう進化させるか」を共有し、研修の意義を“自分ごと”として捉えてもらう工夫が必要です。
2. 「体験」で終わらせず、授業での実践を意識させること
アクティブラーニング研修では、参加者が体験を通して学ぶ機会が多いですが、それだけで終わってしまうと「楽しかった」で終わってしまいます。
研修の最後には、自分の授業にどう取り入れるかを考える時間を設け、単元設計や実践アイデアを具体化できるようにすると効果的です。
3. 参加者同士の対話や交流を促進する環境づくり
アクティブラーニングは「対話」を重視する学習方法です。研修の中でも、教員同士が安心して意見を交わせる雰囲気をつくることが成功の鍵になります。
そのためには、進行役がアイスブレイクを行ったり、否定されないルールの共有、少人数グループでのワークを導入したりといった工夫が求められます。
教員が変われば授業が変わる、そして学校が変わる
アクティブラーニングは単なる「手法」ではなく、学びに対する姿勢を変える「考え方」です。その変革を支えるのが、教職員研修の力です。
教員が“自分ごと”として主体的に学べる環境をつくり、現場での実践につなげることが、これからの学校教育に求められています。
弊社では、実践的かつ効果的なアクティブラーニング研修を提案しています。ぜひ一度ご相談ください。
合わせて読みたい
近年、教育現場では「主体的・対話的で深い学び」が重視されるよう…
近年、教育現場は急速に変化しています。ICTの活用、アクティブ…
デジタル時代において、教育現場でのICT活用は欠かせません。I…
他の記事をみる
 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました 講師候補」から削除されました
講師候補」から削除されました












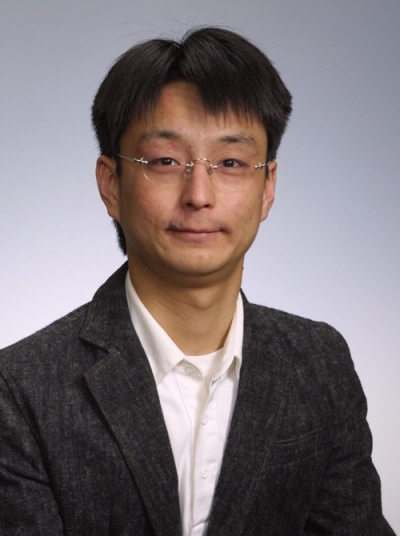















業務外の講師への取次は対応しておりません。