
 単に職場をきれいにするためだけに環境整備(整理・整頓・清掃)を行っていないでしょうか? 実は環境整備には、経費削減や業績アップなど、会社を強くする様々な効果があるのです。
単に職場をきれいにするためだけに環境整備(整理・整頓・清掃)を行っていないでしょうか? 実は環境整備には、経費削減や業績アップなど、会社を強くする様々な効果があるのです。
今回はそんな環境整備の力に気付き、独自メソッドの”そうじ”によって企業の組織変革をサポートしている「株式会社そうじの力」代表取締役の小早祥一郎さんに、”そうじ”の持つ力やそれに着目した経緯や理念について伺いました。
”そうじ”は心を整える実践。2人の師から得た気付き

▲イメージ画像
―― “そうじの力”で組織変革を行うというのは珍しい手法だと思いますが、“そうじ”が組織変革に繋がるとお考えになられたきっかけをお聞かせください。
小早 私が現在の活動をはじめたのは、2人の恩師の存在が大きく影響しています。きっかけは、新卒から12年間勤めた日産自動車株式会社を退職したことです。
エンドユーザーと触れ合う機会の少ない部署だったため、「自分はお客様の役に立っているのか?」という違和感があったのです。そこで直接お客様の困りごとを解決できる整体師になろうとしたのですが、強い志があったわけではなかったため挫折し、無職になってしまいました
そこでご縁があったのが、茨城県で“人間学”道場を開いている1人目の恩師でした。師匠の下で人の行動指針である“人生理念”の作り方を学び、2年ほどかけて人生理念を文章化していきました。
私の人生理念は、「互いに役立ち合う社会の建設に貢献する」「人々の自立と使命追求を支援する」の2つです。これはそのまま弊社の企業理念にもなっています。
しかし自身の理念が明確になったものの、「行動しなければ何にもならない。理念を実現するための実践が必要だ」という考えに至ったのです。
そんなときに尊敬する経営者である2人目の恩師から、「掃除をすると人生が変わるよ」と言われたのです。言われた当初は意味がよく分かりませんでしたが、「とにかくやってみよう」と、我流でトイレ掃除やゴミ拾い、身の回りの整理などをはじめてみました。すると、半年ほどで自分が変化してきたと感じるようになったのです。
その実体験から、「“そうじ”の力で企業経営のお手伝いをしたらおもしろいのではないか」と考え、株式会社そうじの力を立ち上げました。
――掃除やゴミ拾いを続けて感じた変化とは、どのようなものでしたか?
小早 まず気持ちが前向きになりましたし、小さなことをコツコツ続けていくことで大きなことに少しずつ近づいていくような実感や、世の中の物事がよく見えるようになった感覚もありました。
例えば、2~3時間ゴミ拾いをするだけでも、「ゴミの量が多い地域は人が多いだけでなく治安が悪いことが多く、ゴミが少ない地域にはしっかりとしたコミュニティが築かれて自主的に掃除をする文化がある」といった地域の特性が見えてきたのです。
――小早さんが掲げていらっしゃる“そうじ”とは、ただきれいにするための行動ではないようですね。小早さんにとって“そうじ”とはどのようなものですか?
小早 私が掲げている”そうじ”は、単に場をキレイにするだけの”掃除”ではありません。人や組織の意識変革を伴う取り組みを”そうじ”と表現しています。
私にとって“そうじ”とは、自分の心を整えるための実践のひとつです。働く上で仕事に向かう心構えはとても大切なものだと私は考えています。心構えをするには心を整える必要がありますが、心というものは実態がないものです。
実態がない心を整えていくためには、自分の肉体や周りの環境といった物理的なものを整えていくしかありません。そのように、自分の心を整えていくための手段が“そうじ”であると私は考えています。
頭の中が整理できていない方の多くは、過ごす環境も整理できていません。そのため私は、「まず周りをすっきりさせることで頭の中を整理できる」とみなさんにお伝えしています。
実際私がコンサルティングさせていただいた企業の方々からも「“そうじ”を実践してから頭が冴えてきた」というお声を多くいただくので、間違いなく効果があると考えています。
経費削減・生産性UPも叶える”そうじ”の効果と実践のコツ

▲コンサルティングを受けた企業が、小早さんの指導の下“そうじ”の実習を行う様子。(「株式会社そうじの力」公式サイトより)
――“そうじ”は会社組織においてどのような効果をもたらすのでしょうか?
小早 まず、環境が変わることで意識や気持ちが変わるという効果があります。例えばある企業の社長は、ものがあふれた机で仕事していたことで、「常に仕事に追われているようで会社に来るのが憂鬱だ」と話していました。しかし“そうじ”を始めて机上に何も置かないようにしてからはそうしたプレッシャーを感じなくなり、出社するのが楽しくなったそうです。
また、環境を整えることで健全な規律が育つという効果もあります。社内が散らかっている状態では物を大切にしようという気が起きにくいものですが、環境が整えば自然と「物を大切に使おう」「使ったら元の場所に戻そう」という意識になっていきます。
クライアント様から「車をきれいにしたら事故が減った」という声も多く聞かれますが、これも車をきれいにすることで気持ちが整い、落ち着いて運転できるようになるからでしょう。
――意識が変わり規律が育てば、作業効率も上がりそうですね。
小早 実際、1年間“そうじ”に取り組んだだけで2,600万円の経費削減を実現した例もあります。その企業では自社で捌ききれない加工業務を外注業者に依頼していました。しかし“そうじ”によりスペースの余裕が生まれたことで自社対応できるようになり、外注加工費を2,600万円分も削減できたのです。
物が多く手狭な環境ではこなせる作業も限られ、作業効率が落ちてしまいます。“そうじ”によって作業スペースが広くなれば作業効率が上がり、経費削減や売り上げ増も可能になるのです。
――製造業などでは“5S”※に取り組んでいる企業も多いと思いますが、“5S”と”そうじ”はどう違うのでしょうか?
小早 ”そうじ”と“5S”との違いは主に3つあります。
まず、取り組む範囲が異なる点です。“5S”は現場のみで行われて事務所や倉庫までは実施されない場合が多いですが、“そうじ”は場所を問わず会社全体で行います。
2つめは、実施する対象者が限定されていない点です。“5S”は現場従業員のみが行なうことが多いですが、私は、”そうじ”においては社内への影響力が強い経営者がまず取り組み、会社全体で行うことが重要だと考えています。
3つめは、捨てることへの重要度です。”そうじ”では捨てることを特に重視しているため、単なる整理整頓の範囲に留まらず、しっかりと不要なものを捨てるところから始めます。
※製造業などでよく行われている環境整備の取り組み。整理、整頓、清掃、清潔、躾の頭文字を取っている。
――“そうじ”の効果を実感できるようになるには、どれくらいの期間が必要ですか?
小早 まずは1年間取り組めば“そうじ”の基礎ができ、様々な効果も感じられるようになるでしょう。多くの場合、2~3年続ければ組織に“そうじ”の文化がしっかりと定着していきます。
――定着せず失敗してしまうこともありそうですが、成功させるコツはありますか?
小早 最も重要なのは、トップである社長の強い意志です。まずは社長に“そうじ”の重要性や必要性をしっかりと理解していただくことが大切です。
また、楽しくない活動は続かないので、楽しんで取り組むことも重要です。テンションを上げて会社全体の大きなプロジェクトとして取り組んでいく必要がありますが、片手間ではなく集中して取り組むことがポイントです。
そのため私は月に一度、業務をストップさせて“そうじ”だけに取り組む時間を設けることをおすすめしています。イベントのように取り組むことで、「これはしっかり取り組むべきことだ」という意識が芽生えていくのです。
――業務を止めてまで取り組むとなると、反対されることもあるのではないですか?
小早 もちろん社員や幹部たちに反対されることもあります。しかし私は、反対派に焦点を当てないようにとお伝えしています。
「組織において何か新しいことをする際には、2割が賛成派に、6割が中立派に、2割が反対派になる」という“2:6:2の法則”と呼ばれる法則がありますが、全員で取り組むことにこだわって2割の反対派にフォーカスを当ててしまうと、むしろ対立などのマイナスの影響が生まれてしまいます。
まず2割の賛成派を盛り上げていけば、中立派の6割の人も賛成派に傾いていくものです。社内の8割が取り組んでいけば、2割が反対していてもあまり影響はありませんし、反対していた方が賛成派になることもあります。積極的になれない人がいても気にしない方がいいでしょう。
捨てないほうがもったいない!”捨てる経営”が利益をもたらす

▲小早さんの講演会の様子。講演会では、実例写真を見ながら分かりやすく”そうじ”の効果や取り組み方について学べる
――小早さんは『捨てる経営』(出版:スタンダーズ)という著書を出版されるほど、特に“捨てる”ことを重視されていらっしゃいますよね。
小早 物が積み重なってしまう大きな原因は、使っていないものを捨てずにいることです。「捨てるのはもったいない」と言う方もいらっしゃいますが、貴重なスペースを不要なもので埋めてしまう方がもったいないと思います。
不要なものを捨てていくと、埋もれていた不良・長期在庫の数や、何本も同じペンが出てくるような経費の無駄遣いなど、会社の実態や現状がよく見えるようになります。
捨てるのは在庫や身近にある物だけではありません。売れない商品を廃番にして利益率を改善したり、業績の良い頃に増やした支店を統廃合して負担を減らしたり、売上の良い事業だけに絞って成長させたりすることも“捨てる”ということです。これらは会社経営上当たり前の対策のように思えるかもしれませんが、意外と方法論的には難しいものなのです。
――何を捨てるべきかを決断するのは難しいですよね。
小早 おっしゃる通り、重要なのは決断力なのです。私はその決断力を身につけるため、まずは身近で目に見える物理的なものから捨てることをおすすめしています。
商品の廃番や事業縮小のように、物理的に見えづらいものを捨てるのは難しいものです。そのためまず事務用品などの目に見えるものから捨てていくことで、「捨てるといいことがある」というマインドを育てていくのです。そうすれば商品ラインナップや事業といった、物理的に見えづらい不用なものの整理にまで踏み込んでいけるようになっていきます。
段階的に捨てていくことは、経営者の方に必要な決断力や判断力を鍛えるトレーニングにもなるのでおすすめです。
――講演会ではどのようなお話をされていらっしゃいますか?
小早 講演会では“そうじ”による効果の実例を写真でご紹介しながら、“そうじ”を実践する手順やコツなどをお伝えしています。経営者に向けたお話しがメインとはなりますが、講演会の内容は誰が聞いても納得できるお話だと思います。
特に強くお伝えしているのが、トップが強い意思を持つことと、捨てることの重要性です。捨てることをもったいないと感じて“そうじ”が進まない方が多いので、“捨てないことの方がもったいない”ということは繰り返しお伝えしています。
――最後に、小早さんの夢をお聞かせください。
小早 私の夢は、日本中の人が“そうじ”に取り組んでくれることです。日本中で“そうじ”に取り組んでいけば、きれいで住み良い社会になっていくだけでなく、争いが少なく、互いに協力し合える強い社会ができていくのではないかと考えています。
できるだけ多くの方が“そうじ”に取り組むことで、日本が住みやすく、仲の良い国になっていければと思っています。私がその一助になれれば本望です。
――貴重なお話をありがとうございました!
小早祥一郎 こはやしょういちろう
組織活性化コンサルタント

早大卒後、日産勤務。人事・営業・環境各部門の制度改革などに携わる。退職後、「人間学」の師匠の下で自らの人生理念を制定。その後、「掃除道」に取り組み【組織変革支援:そうじ×日産流5S×捨てる】を独自構築。人材・組織・生産性・利益率・離職防止など多方面に貢献、多大な成果をあげている。
|
講師ジャンル
|
実務知識 | 人材・組織マネジメント |
|---|
プランタイトル
組織力をアップさせる!“そうじの力”で組織風土改革
 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました 講師候補」から削除されました
講師候補」から削除されましたあわせて読みたい
『退職代行モームリ』を運営し、そこから得た様々なデータを公開さ…
本人に代わって退職の意思を会社に伝える退職代行。ここ数年で一気…
ディズニーキャスト※の優れた対応は有名ですが、キャストが優秀と…
他の記事をみる







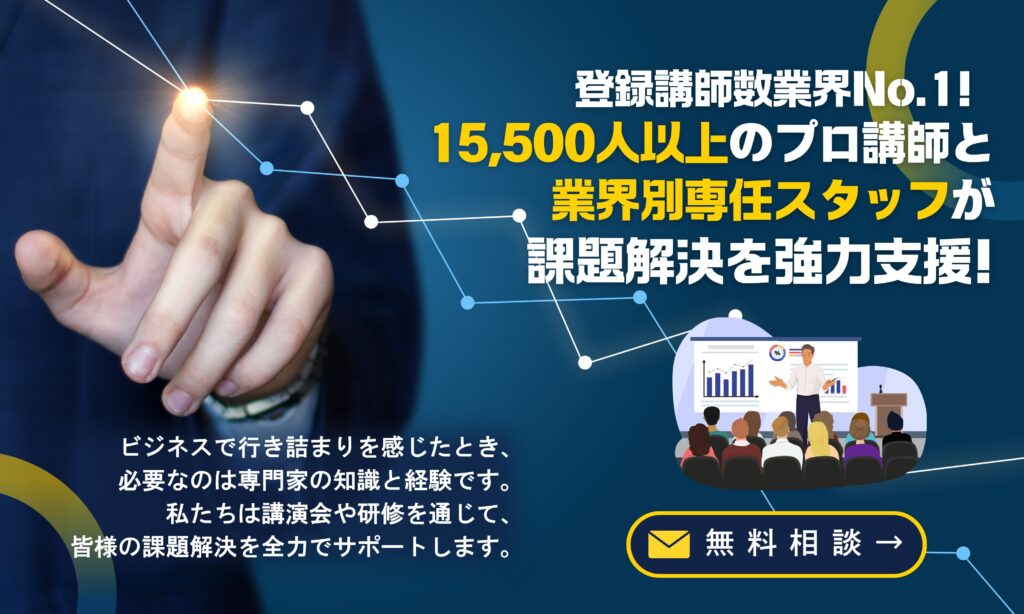











業務外の講師への取次は対応しておりません。