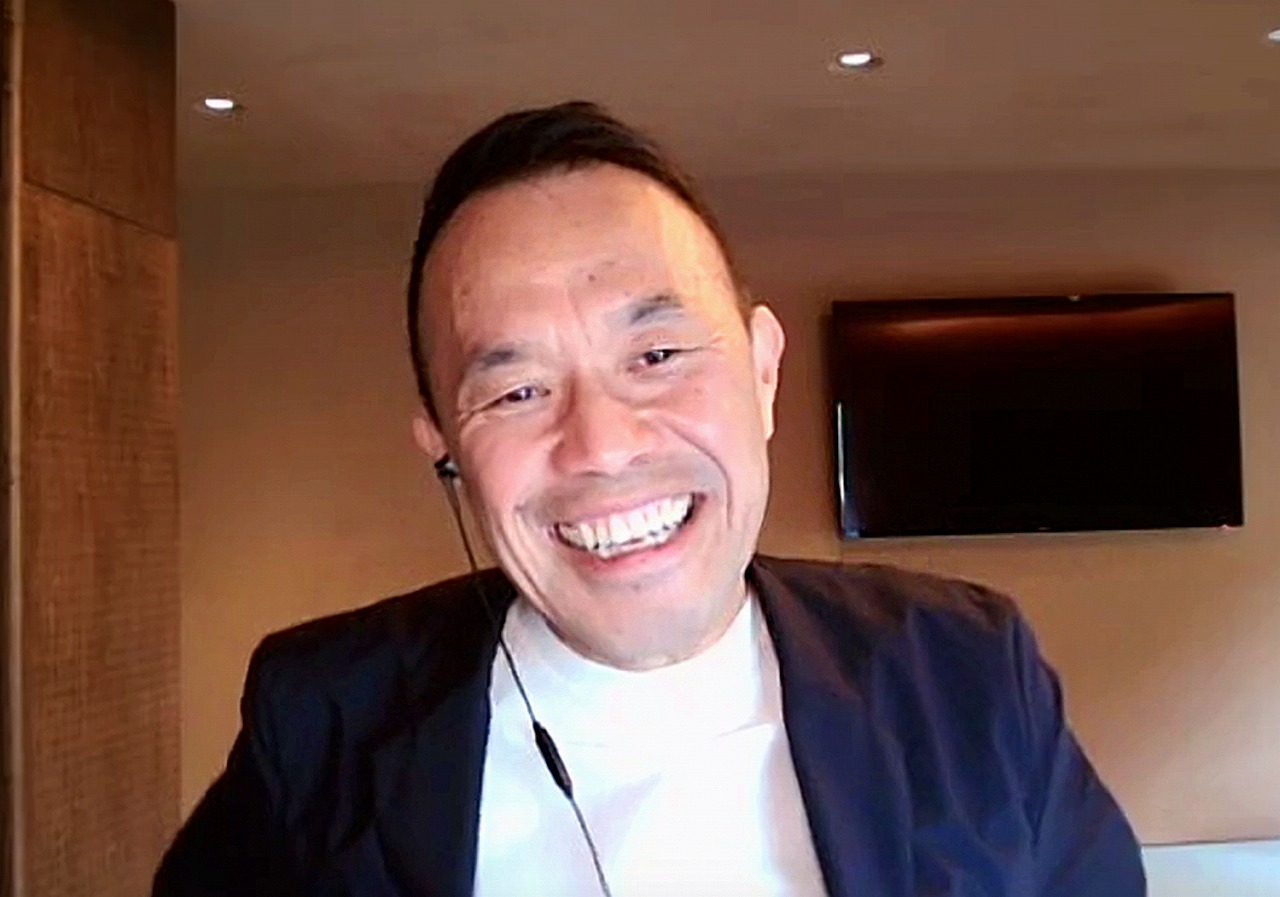

ディズニーキャスト※の優れた対応は有名ですが、キャストが優秀ということは、優れた人材教育がされているということです。
今回はディズニーで20年間人材教育に携わり、ディズニーメソッドによる組織作りを広めている大住力(おおすみ りき)さんに、ディズニーでの経験から得た学びやディズニーメソッドの魅力についてお聞きしました。
※ディズニーリゾートで働くスタッフのこと
人生を変えた「ギブハピネス」との出会い
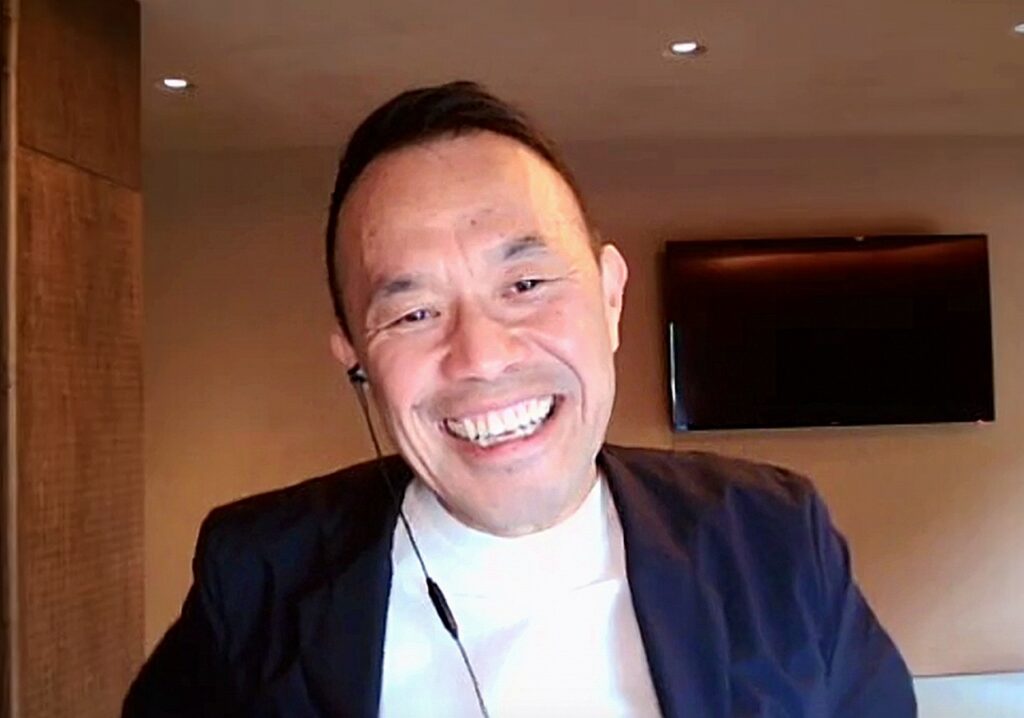 ――大住さんは元々ディズニーがお好きで”株式会社オリエンタルランド”に入社されたのですか?
――大住さんは元々ディズニーがお好きで”株式会社オリエンタルランド”に入社されたのですか?
大住 元々ディズニーに興味があったわけではなく、昔はサッカー選手を目指していました。しかし19歳で怪我によりサッカー選手の道を諦めざるを得なくなったのです。
そこから何事に対しても熱が入らなくなってしまい、就職する時期になってもやりたいことが定まりませんでした。そんな時にたまたま遊びに行ったディズニーランドで”ワンマンズ・ドリーム”というショーを観たことが、オリエンタルランドに入社するきっかけになりました。
私の心を動かしたのはショーそのものではなく、観客の様子でした。私の前列にいた老夫婦が、なんとも嬉しそうな顔をしてショーを観ていたのです。
夢を諦めて拗ねていた中で見たあの老夫婦の笑顔は、今でも忘れられません。「ディズニーの仕事は、人をこんなにいい笑顔にするのか」と感動し、すぐにディズニーについて調べました。
ディズニーの理念は、「ギブハピネス(Give Happiness)」というワンワードに集約されています。この“人に幸せを提供する”という理念が自分にピッタリとはまり、久々に行き先が決まったような感覚になりました。
「自分も人に幸せを提供する人間になりたい」と考えてオリエンタルランドに入社し、ディズニーの仕事にのめりこんでいったのです。
――「ギブハピネス」が体現されている瞬間を見られたのですね。オリエンタルランドではどのようなお仕事をされていらっしゃいましたか?
大住 最初はジャングルクルーズの船長など、アトラクションの現場クルーからスタートしました。その後レストランやショップなどでの研修を経て東京ディズニーシーやイクスピアリの開発も担当しましたが、在籍した20年間、一貫して携わってきたのは人材教育です。
中でもイクスピアリでの人材教育の経験は、私にとって非常に大きなものとなりました。イクスピアリはディズニーリゾート内にあるショッピングモールなので、ディズニーストア以外のテナントの方々にもディズニー流のサービスを提供していただく必要があります。
どうすれば外部企業の方にもディズニー流のサービスを理解して実践いただけるのか、指導する立場としてとても考えさせられた経験でした。
――その経験が現在の活動へと続いているのですね。長く勤めたオリエンタルランドを退社し、”公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を”を立ち上げられたのはなぜですか?
大住 実はイクスピアリの開発で社外の方々と関わったことで、「世の中にはすごい人がいる。ディズニーの枠から出て、もっと自分を試してみたい」と考えるようになったのです。
そんなときに研修のため訪れたフロリダで、難病の子どものための非営利リゾート施設”ギブ・キッズ・ザ・ワールド・ビレッジ”を設立したヘンリー・ランドワース氏に出会ったのが、”難病の子どもとその家族へ夢を”を設立するきっかけになりました。
”難病の子どもとその家族へ夢を”は、難病の子を持つ家族を支援するための団体です。難病の子の支援は医療のプロが行います。医療のプロではない自分ができることは何だろうと考えた結果、家族の支援をしている団体がないことに気付いたのです。
子どもの難病が分かると、「健康に産んであげられなかった」と自分を責めてしまうお母さんがたくさんいます。偏見を受けたり、心配させないよう友人にも相談できなかったりと、社会から孤立してしまうご家族も多いものです。
そんなお母さんやご家族が少しでも悩みから解放される時間を作れるよう、私たちは難病の子とそのご家族を地域全体で迎え入れる“ウィッシュ・バケーション(家族全員旅行)”の無償提供や、自宅への看護師派遣などの活動を行っています。

▲公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を”の活動風景(画像:大住さん提供)
――”難病の子どもとその家族へ夢を”だけでなく、”一般社団法人 ソコリキ教育研究所”も設立されたのはなぜですか?
大住 2010年に”難病の子どもとその家族へ夢を”を立ち上げたのですが、2011年に発生した東日本大震災により、すべてのスポンサーが被災地支援のために離れてしまったのです。
非営利団体である公益社団法人にとって、資金不足はとても怖いものです。安定して活動を続けていくためにはスポンサーに頼るばかりでなく自分たちで資金を作る必要があると考え、ディズニーでの人材教育の経験を活かした”ソコリキ教育研究所”を設立しました。
”ソコリキ教育研究所”の主な事業は、ディズニーメソッドを企業に伝え、人材教育を支援することです。講演会やセミナーに加え、より深く取り組みたい企業様には、マニュアル作成や手法の指導などのコンサルティングも行っています。
ベクトルを合わせて組織力を高めるディズニー流マニュアル作り

▲イメージ画像
――大住さんが学ばれてきたディズニーメソッドと一般的な人材教育とでは、どのような違いがあるのでしょうか?
大住 大きな特徴としては、組織全体に「安心感を作る」「緊張感を作る」「原点回帰を促す」の3つです。例えばディズニーには、 “ブラザーシステム”というものが導入されています。
これは新入社員一人ひとりにマンツーマンで指導する先輩社員が付く制度です。日本で言う“アニキ制度”ですね。新人研修を終えたら完全に独り立ちする企業も多いですが、ディズニーでは新人研修後も先輩社員が相談役としてずっと付いています。プライベートも含め何でも相談できるシステムなので、新入社員は安心して仕事に向かうことができます。
一方、後輩を指導する中間層の社員には、ずっと指導役としての責任が求められます。年次を積んで仕事に慣れると油断が生じやすいものですが、ブラザーシステムにより指導役としての緊張感が生まれることで、仕事や職場全体が活性化していくのです。
さらに年次が進んで現場を離れ、幹部層や経営層になると、「自分の会社は何のために存在し、何を社会に提供していくのか」という原点を忘れてしまいがちです。そのためディズニーでは原点回帰を促すことを大切にしています。ブラザーシステムで後輩をサポートするのも、自分が辿ってきた経験を思い出すという原点回帰のひとつになっています。
――ディズニーメソッドはビジネスシーンにおいてどのような効果があるのでしょうか?
大住 最も大きな効果は、組織力が高まることです。ディズニーでは個の力ではなく、チームという組織の力で目標に向かっていくことを重視しています。しかし仲間と共に働くというのは、実はとても難しいものなのです。
そのためディズニーメソッドでは、チームのマニュアル作りを大切にしています。ディズニーにおけるマニュアルとは、いわゆる常識のことです。
組織の人間関係において、初対面から嫌いな人はいませんよね。大概は一緒に仕事をしていくうちに徐々に合わない点や気になる点が見えてきて、嫌いになってしまうのではないでしょうか。これは「当然こうするだろう」と思う常識が、人によって異なることで起こります。しかしディズニーでは、一人ひとり常識が違って当たり前だと考えられているのです。
一人ひとり常識が違うのは当たり前ですが、それは個人の常識であり、チームの常識ではありません。だからこそディズニーメソッドでは、マニュアルを作って共通の常識をみんなで浸透させていくのです。
チーム皆が同じ常識の下で、当たり前のように同じ動きができるようになれば、とても気持ちのいい会社や組織になっていきます。
――マニュアルにより全員が同じベクトルに向かっていけば、無駄がなくなり業務が効率化しそうですね。
大住 ディズニーでは「エフィシェンシー(Efficiency)」と言いますが、まさしく効率は働く上で非常に大切なものです。組織で協力して取り組んでいる中で違う方向に向かっている人がいると、とても疲れますよね。全員が同じ方向に向かえるというのは、本当にすっきりします。
マニュアルを作るというのは、常識を作るだけでなく効率も考えていくということです。ディズニーでは、声を掛けるタイミングや聞き方一つでゲスト(パークの入園者)の動きが大きく変わります。そのため、ただ闇雲にルールを加えていくのではなく、効率的な方法やタイミングなども含めてマニュアルを作るのです。
弊社では、そうしたディズニー流マニュアルの作り方に加え、指導方法やメソッドを継続していくための方法などもお伝えしています。
人も自分も幸せに。ディズニーメソッドで会社や仕事を好きになる

▲大住さんの講演会の様子。ディズニーメソッドを利用した人材教育のお話をメインに、様々なテーマで講演会を行っている(画像:大住さん提供)
――講演会ではどのようなお話をされていますか?
大住 多くはコミュニケーション方法や組織論など、ディズニーメソッドを利用した人材教育に関するお話です。私の講演会では、企業の方に必ず「何に悩んでいますか?」「御社の課題はどこにあるとお考えですか?」と事前にお聞きしています。
企業によって悩みは様々ですが、問題を掘り下げてみると、その原因はコミュニケーションの欠如であることが多いものです。ディズニーメソッドには、そうしたコミュニケーションの欠如を防ぎ、組織における様々な問題に総じて対応できる仕組みが入っています。
“ディズニー”の名からサービス業向きのように思われるかもしれませんが、ディズニーメソッドはどのような業界・業種・業態の方にも役立つ組織論です。講演会も、多種多様な業界・業種の方からご依頼いただいています。
講演会で特に私が大切にしているのは、その自分たちの会社の良いところや社会的役割、価値に気付いていただくことです。仕事に慣れてくると毎日が当たり前に感じて飽きてしまい、会社を嫌いになって辞めたくなってしまうものなので、会社の良いところや社会的役割、価値に気付いてもらうことはとても重要なのです。これも原点回帰ですね。講演会の後には、「うちの会社、良いじゃないか」という声がよく聞こえてきます。
人材教育の話だけでなく、難病のご家族との関わりから学んだ“生き方”に関する話もさせていただくミックス型の講演依頼も多くいただきます。世の中には「このままこの組織にいて良いのか」と悩んでいる方も多くいらっしゃるので、「どう生きていくか」「何のために生きていくか」というお話しへの関心度は高いと感じています。
――最後に、大住さんの夢をお聞かせください。
大住 ウォルト・ディズニーの「ギブハピネス」という言葉は、改めて考えてみると「人に幸せを提供したら、自分も幸せになれる」という意味でした。いちばんの幸せは周りの人が笑顔になることだと、私は最近よく思います。
自分の仕事によって人が笑顔になる。それを思い浮かべながら仕事をしていくことが自分の幸せになっていく。そう思えるようになりました。
また、ディズニーには「リブラッキー(Live Lucky)」という言葉もあります。これは「後悔せず生きる」という意味です。「Lucky」には「幸運を待つ」という意味もありますが、「幸運を掴みにいく」という意味もあります。
その場に留まるのは安全かもしれませんが、どうなるか分からないけれど一歩踏み出してやってみるのも、幸運を引き寄せるやり方だと思います。
「ギブハピネス」と「リブラッキー」。この2つの大好きなディズニーの言葉を皆様にお送りして、私自身も成長し、皆様に幸せと幸運を感じていただきたいと思っています。
――貴重なお話をありがとうございました!
大住 力 おおすみりき
公益社団法人難病の子どもとその家族へ夢を 代表 ソコリキ教育研究所 所長

東京ディズニーランドを管理する(株)オリエンタルランドにて約20年間、人材教育、プロジェクトの運営、マネジメントに携わる。現在は、企業や教育現場の人材育成、難病と闘う子どもとその家族全員を応援する活動、また、ホスピタリティー、コミュニケーション、モチベーションなどをテーマに講演活動も行う。
|
講師ジャンル
|
ビジネス教養 | その他ビジネストピック | ライフプラン |
|---|---|---|---|
| ソフトスキル | 意識改革 | モチベーション | |
| コミュニケーション | |||
| 実務知識 | 顧客満足・クレーム対応 | 人材・組織マネジメント | |
| 社会啓発 | 人権・平和 |
プランタイトル
【ホスピタリティ】 ディズニーの現場力
 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました 講師候補」から削除されました
講師候補」から削除されましたあわせて読みたい
『退職代行モームリ』を運営し、そこから得た様々なデータを公開さ…
本人に代わって退職の意思を会社に伝える退職代行。ここ数年で一気…
ディズニーキャスト※の優れた対応は有名ですが、キャストが優秀と…
他の記事をみる







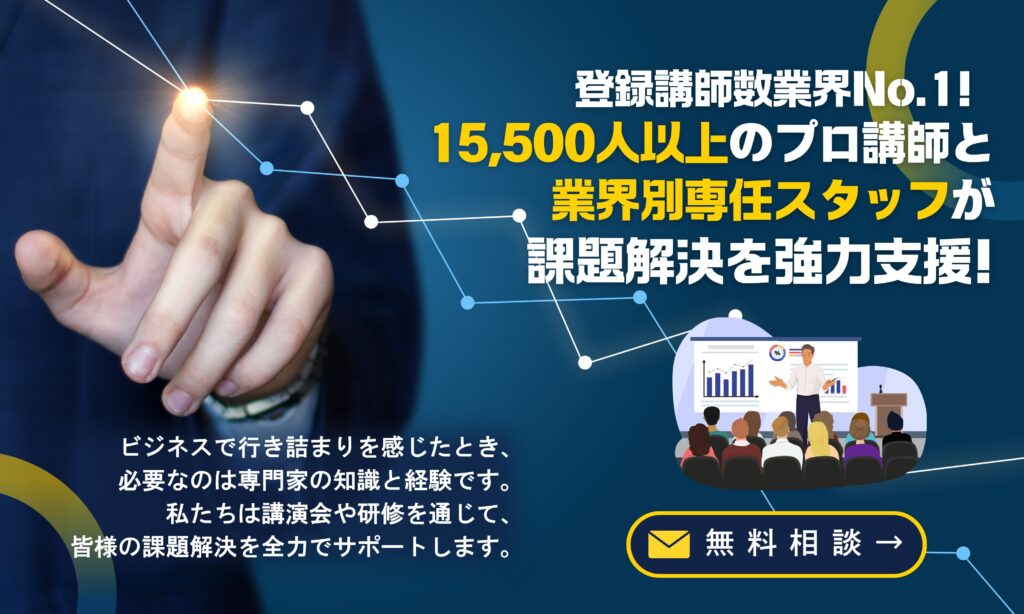











業務外の講師への取次は対応しておりません。