
2022年に中小企業でもパワーハラスメント防止対策が義務化されました。パワーハラスメント(パワハラ)は、従業員の士気を低下させ、メンタルヘルスの不調を引き起こし、最悪の場合、離職にもつながる可能性があります。少子化が進み、人材不足が加速する中で、パワハラが組織の生産性を低下させる要因となることを考えれば、早期に予防策を講じることが重要です。
今回は、『部下が変わる本当の叱り方』の著者であり、人材育成・組織改革コンサルタントとして活躍する吉田裕児氏に、パワハラ上司から慕われる上司へと変わるための意識改革についてお話を伺いました。
 【監修・取材先】
【監修・取材先】
吉田裕児氏
建設現場の事故防止コンサルタント
人と組織を咲かせる人財育成コーチ
リスク回避だけのパワハラ防止対策では不十分
現在、多くの企業がパワハラ防止対策に取り組んでいます。かつては職場で上司が部下を怒鳴ったり、強い言葉を使ったりする場面が珍しくありませんでしたが、昨今ではそのような光景は減ってきました。しかし、その反動として「パワハラと誤解されるのが怖い」と指導を控える管理職が増え、職場の規律が緩み、生産性が低下するという新たな課題も生まれています。
一見、部下にとっては気軽で居心地の良い職場になるかもしれませんが、上司が適切な指導をしないことで、部下は成長の機会を失い、職場全体のモチベーションも低下しがちです。最終的に、「この環境では成長できない」と感じた社員が離職するケースも少なくありません。
では、どのようにすれば適切な指導を行いながら、パワハラを防止できるのでしょうか?
パワハラ防止の鍵は、チームのゴールを共有すること

企業には「社会に価値を提供する」という目的があり、上司も部下もその目標に向かって共に進むチームの一員です。まずは、チームとしてのゴールを明確にし、メンバーと共有することが大切です。
上司は、単に指示を与えるのではなく、「私たちは何を目指すのか」とチームのゴールを発信し、部下の考えや希望を聞きながら対話を通じてゴールをすり合わせていく必要があります。部下が「自分の成長がチームの目標達成につながる」と実感できれば、業務への主体性が生まれ、指導も受け入れやすくなります。
上司は、部下がチームの方向性から外れたときは指摘し、成果を上げたときには適切に評価することで、信頼関係を築くことができます。
例えば、部下にはそれぞれにキャリアの理想像があります。将来どのようなキャリアを築きたいのか、そのために今どのような経験を積みたいのか部下の希望を引き出します。そして、その希望をチームの目指すゴールへとつなげることができないか、一緒に考えるのです。
そうやって最初に部下の希望とチームの方向性をすり合わせておけば、部下は業務におけるすべてを「自分ごと」として捉えられるようになります。上司は、チームの方向性から部下が外れているときには「そっちは違うよ。戻っておいで」と指摘してあげ、役割をしっかりと果たしているときには「いいね!できているね」と一緒に喜んであげましょう。部下は自分のことをわかってくれていると理解し、上司の言葉を受け入れやすくなります。
パワハラ防止の第一歩は、上司と部下の間にチームとしての信頼関係を築くことなのです。
パワハラ上司を脱却する「言葉・行動・意識」の3つのスイッチ

パワハラのリスクがある今、長年部下に厳しい態度をとってきた管理職は、部下と積極的に関わることを躊躇してしまうかもしれません。だからと言って部下との対話を避け続けていても、真の解決にはなりません。
パワハラを防止しながら適切な指導を行うためには、次の3つのスイッチを入れることが重要です。
①言葉スイッチ:部下を認めるコミュニケーション
日々の言葉遣いを意識することで、関係性を大きく変えることができます。まずは「相手を認める」言葉のスイッチを入れてみましょう。
例えば、部下に話しかけるとき、必ず相手の名前を呼ぶようにします。人は名前を呼ばれるだけで、「相手が自分の存在を認めてくれている」と感じます。
また、一方的に命令したり叱責したりするのではなく、「あなたはどう思う?」と問いかけるように話すこともポイントです。部下は意見を求められることで、自分を認められていると感じると同時に、自分の頭で考えるようになって主体性が生まれます。
そして部下が自分の考えを述べたときに、「そう考えているんだね」と否定せず共感する姿勢も重要です。共感された部下は安心することができ、自ら間違いに気づくこともできます。
②行動スイッチ:信頼を築くフォローアップ
言葉の次に、部下から信頼を得られるような行動スイッチを入れてみましょう。
例えば、部下の間違いを指摘した場合は、必ず時間を置いてからフォローします。これは自分が言ったことを部下が理解しているかを確認するためです。部下が目指すべき方向から外れてしまった場合、正しい道筋に戻るまでしっかり見届けることが大切です。また、部下にも何か言い分があるかもしれません。フォローしながら部下の言葉にも耳を傾けます。
さらに「自分の考えと事実とを分ける」という行動習慣も重要です。部下が業務中にずっと下を向いているとき、反射的に「仕事に対してやる気がない」と判断して、部下に厳しくあたる上司もいます。しかし、実際には部下は体調が悪かったり、何か悩みを抱えていたりするのかもしれません。上司は、自身の思い込みを排除し、必ず事実を確認するという習慣を身に付けましょう。
このような行動が、上司と部下の信頼関係を強化します。
③意識スイッチ:部下の成長を支えるマインドセット
上司の言葉が変われば行動が変わり、最終的には上司自身の意識も変わります。
パワハラとされる行動に陥りやすい上司は、無意識のうちに「部下は仕事の駒」と考えています。しかし部下は1人の人間です。部下を1人の人間だと意識することができれば、部下を尊重し、主体性や成長意欲を引き出すことができます。部下に不足しているスキルも、成長の「伸びしろ」として捉え、成長を後押しできるようになるでしょう。
最終的には、部下自身の「チームの一員としてゴールを目指したい、自分の役割を全うしたい」という意欲を引き出すほうが、パワハラで無理やり従わせるよりもずっと高いパフォーマンスが得られるということにも気づけるはずです。
パワハラ防止には、互いを認め合う職場の意識づくりが大切
 職場のパワハラを防止するには、上司が「言葉・行動・意識」の3つの観点から自分自身のあり方を見つめることが大切です。そして部下を変えるのではなく、自分を変えることが重要なのだと気づくことで、部下との信頼関係を構築できます。
職場のパワハラを防止するには、上司が「言葉・行動・意識」の3つの観点から自分自身のあり方を見つめることが大切です。そして部下を変えるのではなく、自分を変えることが重要なのだと気づくことで、部下との信頼関係を構築できます。
従来の、メンバーより一段高いところから命令を下し、パフォーマンスの低いメンバーを叱責してチームを率いていくリーダー像は、現在の職場には適しません。これからの時代に求められているのは、メンバーと対話し、互いを認め合いながら共にゴールを目指すリーダーです。
今回お話を聞かせていただいた吉田氏も、かつて建設現場の責任者として働く中で、部下への誤った指導方法が原因で現場の生産性を大きく低下させてしまったという実体験を持っています。その経験から、企業の経営者や管理職向けに、部下が本気で頑張れるようになる指導方法について講演活動を行っています。吉田氏の講演ではパワハラ防止と職場の士気向上を両立させた、理想の職場づくりについて学ぶことができます。
「パワハラ防止に取り組みたいが、職場の緩みが心配」とお考えの方へ、今こそ組織の活性化につながるリーダーシップを実践してみませんか!
吉田裕児 よしだゆうじ
建設現場の事故防止コンサルタント 人と組織を咲かせる人財育成コーチ

西松建設現場所長として作業員・スタッフを指導。出世街道まっしぐらの中、部下の指導法を間違えたことで、現場が大赤字に。第一線から外されるも一念発起し、「人を活かす叱り方」を探究。現在、「社長・社員・顧客が本音で語り合い本気で頑張れる会社づくり」を支援。著書『部下が変わる本当の叱り方』。
|
講師ジャンル
|
ソフトスキル | コミュニケーション | リーダーシップ |
|---|---|---|---|
| 実務知識 | 安全管理・労働災害 | 人材・組織マネジメント |
プランタイトル
パワハラ防止と社員のやる気アップを同時に実現させる本当の叱り方
~社員を自律に導くコミュニケーション術~
あわせて読みたい
営業研修はなかなかうまくいかない、失敗するという声がよく聞かれ…
営業スキルとは「コミュニケーションスキル」と言っても過言ではあ…
数ある商品の中から選び買って頂くために必要な営業ノウハウとは?…
他の記事をみる
 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました 講師候補」から削除されました
講師候補」から削除されました








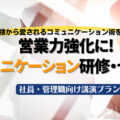









業務外の講師への取次は対応しておりません。