想定する対象者
教育関係者、子ども支援関係者、子育て当事者など
提供する価値・伝えたい事
不登校の小中学生は全国で30万人を超え、学校に行かないことは今や特別なことではありません。不登校はネガティブなことではなく、その子に合った学びの場、学びのあり方を選択する良いきっかけでもあります。ただ、多くの場合、その子の居場所や適した学びのあり方が見つからず、かえって勉強への苦手意識や自己否定的な感情が生まれるきっかけになってしまう現状があります。
演者自身、小学1年から不登校で、山の中で自由に遊んで育ちました。その後、自然への好奇心から、高卒認定(大検)を受け、東京農大に進学することを選びます。あくまで一事例ではありますが、私の実体験をお話しすることで、子どもに合った学びのあり方とは何かを考えることにつなげます。
内 容
1.はじめに
・自己紹介
・ネイチャーライターとしての活動
・フリースクール講師としての活動
・「学ぶ」「遊ぶ」はどう違う?
2.私の子ども時代
・東京生まれ、3人兄弟の末っ子
・小学1年の途中で学校に行かないことを選ぶ
・大分県に引っ越し、山中で過ごした子ども時代
・消しゴム人形での遊びから始まった展開
・パソコンでのプログラミング
・大学進学に向けた、初めての「勉強」
3.あらためて考える「遊ぶ」「学ぶ」
・「遊ぶ」「学ぶ」は対立しない
・数学も遊べる
・勉強が嫌いになる方法
・勉強だけが学びではない
・学校だけが学びの場ではない
・必要なのは、居場所
4.おわりに
・私の実体験はあくまで一事例
・不登校は十人十色
・大学進学という道も、たまたま
・好きなものと出会うこと 好きを探求し続けること
・色々な選択肢、多様な学びの場の必要性
・質疑応答
根拠・関連する活動歴
演者自身が小学1年のころに不登校になり、大学入学までのあいだ、ホームスクーリング(在宅学習)で過ごしていた。
著書『マイマイ計画ブック かたつむり生活入門』(Pヴァイン)
フリースクールでの野外フィールドワークの実践を8年以上継続し、そのほか子どもの居場所や遊び場づくりに長年携わっている。








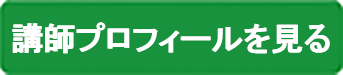


 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました













業務外の講師への取次は対応しておりません。