想定する対象者
ビジネスリーダー、マネジメント層(人間関係・組織づくりに悩む方)
教育関係者、福祉・医療・ケアワーカー(人と人との関係に向き合う職種)
自治体関係者や地域コミュニティの担い手
ライフスタイルやウェルビーイングに関心のある一般市民
多忙の中で「整える」時間や感覚を求めている現代人全般
提供する価値・伝えたい事
この講演では、「神道における“調える”という習慣が、現代人の生活・人間関係・心にどう役立つか」をお伝えします。
・空間を整えることが心を整えることにつながる理由
・人との間(ま)を整えることで関係性が深まる仕組み
・自然のリズムや感性に沿って生きる「日本的ウェルビーイング」
・神道の儀礼に学ぶ、言葉ではなく「儀礼コミュニケーション」
「頑張る」よりも「調える」。
「変える」よりも「調える」。
そんな静かな実践が、複雑な時代をしなやかに生きる力になる――。
神職としての経験と、グローバルな視点を持って、その哲学と具体的な実践法をお届けします
内 容
「調える」とは何か──神道における調和の思想
・掃除、祓え、礼──「整える所作」がもたらす心の変化
・「間を結ぶ」という視点から人間関係を見直す
空間をととのえる:神道的空間デザインの知恵
・日常の中に「聖域」を生み出す工夫
・職場や家庭でも実践できる「調える」習慣
時間をととのえる:中今に生きる知恵
・過去でも未来でもなく、“いまここ”に意識を向ける
・リセットとリズムで暮らしに余白を生む
関係をととのえる:つながりを“結ぶ”感性
・競争ではなく共存を生む、“支配しない関係性”
・所属や役割を越えた“間柄”の在り方
実践の提案:Shinto Momentsを暮らしに取り入れる
・五感を開く/礼をする/自然と共に呼吸する/感謝をかたちにする
・儀礼のある暮らしが、心身を再調律す
根拠・関連する活動歴
・英国大学院にて宗教・文化・神道について研究。異文化環境において神道の本質を再確認
・国際会議(G20宗教フォーラムなど)や国内外の講演で「日本的感性」や「調和の知恵」を発信








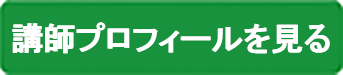


 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました













業務外の講師への取次は対応しておりません。