想定する対象者
・これから子どもを育てようと思っている人
・今、子育てをしている人
(一般市民・保育系の大学生・父母・祖父祖母など)
提供する価値・伝えたい事
絵本は心の栄養。
教職を43年、多くの子どもたちと関わる中、自分で考えて行動できる子どもの共通項目を発見しました。
それは幼いころから読み聞かせの習慣がある環境で育ち、活字から知恵や勇気をもらえる人であることでした。
特に三つ子の魂100までといわれるように、0歳からの読み聞かせをすることにより親子の絆が深くなり親子が安全安心な基地となり心根となります。子どもが大人の膝に乗ってきてくれる時期は、人生の中でも短い期間です。絵本で文字を学ばせようとするのではなく、絵本の持つ魅力を親子で楽しむことで、豊かな感性や知性の基礎が広がります。
内 容
三匹のこぶた 原作の冒頭を朗読「むかしむかし・・・けれどおかあさんぶたは貧しくて・・・
よい絵本の条件
よい絵本の選び方
読み聞かせの効果 子ども・親・祖父母
本が好きな子どもになる環境づくり
本が好きな子どもに育てるためには、環境の工夫がとても大切です。モンテッソーリ教育の視点も取り入れながら、子どもが自然に本と親しめる環境づくりのポイントを紹介します。
1. 本を手に取りやすい環境を作る
📚 「本は特別なもの」ではなく「身近なもの」にすることが大事!
① 低い本棚を用意する
子どもの目線に合わせた高さの本棚を用意する。
表紙が見えるように収納すると、興味を引きやすい(フェイスアウト収納)。
② いろんな場所に本を置く
リビング、寝室、キッチンなど、家のあちこちに本を置く。
トイレや車の中にも小さな絵本を置いてみる。
③ 「読書コーナー」を作る
ふわふわのクッションや絨毯を敷いた、くつろげる読書スペースを用意する。
照明を工夫して、落ち着いて読める雰囲気を作る。
2. 大人が「本を楽しむ姿」を見せる
子どもは大人の真似をして育つ!
親や周りの大人が本を読んでいる姿を見せる。
子どものそばで「この本面白いなぁ」とつぶやく。
休日には「本屋さんに行く」「図書館に行く」を習慣にする。
「一緒に読む」ことも大切!
毎日5分でもいいので、読み聞かせの時間を作る。
「どの本を読もうか?」と選ぶ時間も楽しむ。
子どもが途中で話し出してもOK!会話を楽しみながら読む。
3. 子どもの興味に合った本を選ぶ
「何を読むか」より「楽しい!」が大事
年齢や発達に合った本を選ぶ(モンテッソーリではリアルな写真や具体的な話が好まれる)。
子どもが興味を持っているテーマの本を探す(動物、車、食べ物など)。
文字が少なくても、絵が楽しい本ならOK!
バリエーションも大切!
絵本、図鑑、物語、詩、迷路ブック、しかけ絵本など、いろんな種類を試す。
「大人の本」も興味があれば触れさせる(新聞、料理本、旅行雑誌など)。
4. 本を通じた「楽しい体験」を増やす
🌳 「本を読む=楽しいこと」と感じられる経験を!
本の内容を体験する
動物の本を読んだ後に動物園へ行く
お料理の本を見ながら一緒に料理する
乗り物の本を読んでから電車やバスに乗る
お話を作る・演じる
絵本の続きを子どもと一緒に考えてみる
ぬいぐるみやおもちゃを使って物語を再現する
読書イベントに参加する
図書館の読み聞かせ会に行く
本にまつわる工作やワークショップに参加する
5. 本を「買う」より「選ぶ」経験を
🏪 本は「与えられるもの」ではなく「自分で選ぶもの」
図書館や本屋さんで子ども自身に本を選ばせる。
「何冊でもOK!」ではなく、「今日は1冊だけ選ぼうね」とすると、選ぶ楽しさが増す。
「プレゼントとして本を贈る」習慣をつける(誕生日やクリスマスに本をプレゼントする)。
まとめ
本好きな子どもに育つ環境づくりのポイント
✅ 手に取りやすい環境を作る(低い本棚・読書コーナー)
✅ 大人が本を楽しむ姿を見せる(一緒に読む・図書館や本屋へ行く)
✅ 興味に合った本を選ぶ(動物・乗り物・料理など)
✅ 読書を楽しい体験につなげる(本の内容を体験する・演じる)
✅ 本を「選ぶ経験」を大切にする(自分で選ぶ・プレゼントする)
こうした環境を整えることで、子どもは自然と本を好きになっていきます
根拠・関連する活動歴
JCI 日本青年会議所で地域貢献として「読み聞かせボランティア」理事長賞受賞
文部科学大臣優秀教職員表彰「効果のある学校」
・現在も毎日、園児に厳選された良書を読み聞かせ、絵本に触れて自分で考える子どもを育成中








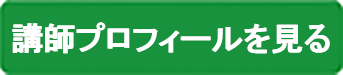


 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました


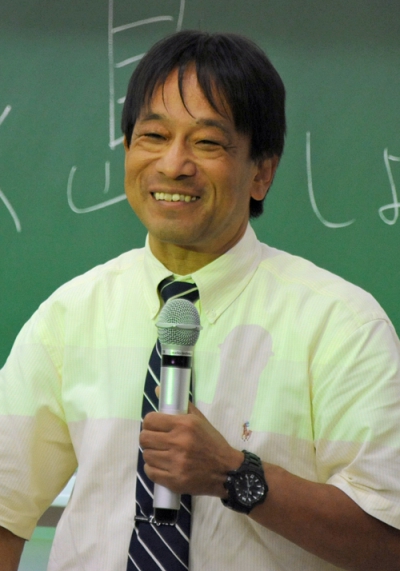










業務外の講師への取次は対応しておりません。