想定する対象者
子育てに関わる全ての人(親、祖父母、教師、コーチなど)
提供する価値・伝えたい事
マインドセット(mindset)とは、物事に対する「考え方の枠組み」や「思考の習慣」のことを指します。
その人が持っている価値観や信念、思考パターンのことです。
例えば、同じ状況でも人によって捉え方が違うのは、マインドセットが異なるからです。
• 「失敗=成長のチャンス」と考える人は、挑戦を続ける。
• 「失敗=恥ずかしいこと」と考える人は、新しいことに挑戦しにくくなる。
つまり、どんなマインドセットを持つかによって、行動や結果が変わってくるのです。
つい強い口調になる。子どもが言うことを聞かない。などの悩みは多いですが、まずは、子育て上手の親のマインドセット(成長思考)について質問させてください。
質問1 「大人が上、子どもが下」と思っていませんか?
子どもも人格を持った一人の人間です。子どもは自立に向けて全力です。今日は発達をしなくていいや。言葉が話せなくてもいい。などと発達をあきらめたりする子どもはいません。子どもにとっては、人生は初めてのことばかり。だからこそ、失敗は成功の素と考えられる成長思考を持たせてあげたいものです。
質問2 大人が「うちの子はこうだから。」と決めつけていませんか?
子どもは、試行錯誤しながら全くさぼらずに(さぼることはまだ知らない)成長しようとしているのに、大人が小さな変化や小さな勇気に気づけずに、結果だけをみて「何度も言ってるでしょ!いつも言っているでしょ!」と大人が一度決めたバイアス《偏った思い込み》で勇気をくじいていることがあります。親子ともども、余裕をもって、日々絶賛成長中!と信じるマインドが必要です。
質問3 大人が自分を優先することにうしろめたさはありませんか?
子どもを産み育てるのには、膨大な時間とエネルギーが必要です。特に幼児の頃は、いつも寝不足、食事もサッと済まさないといけません。特に慢性的に寝不足が続くと親の生命を維持することに精いっぱいで、感情をコントロールできなくなり、「あー、また怒鳴ってしまった。と自己嫌悪におちいることになります。また、「一人の時間なんてない!」と親になって「おかあさん」「おとうさん」という役割が自分のすべてになり、自分が幼いころから積み上げてきたアイデンティティーに向き合う時間が減ってしまい、生き生きした自分を失いがちです。だからこそ、私たち大人は自身の心身を充実させておく必要があるのです。自分を犠牲にすることが当たり前。自分をいたわる暇なんてないようでは、子どもの育ちを助けることはできません。大人が満たされていて幸せだと、子どもにも必ず伝わり、早く素敵な大人になりたいと感じることでしょう。
質問4 完璧をめざして、息苦しくなっていませんか?
あー、今日も片づけずに終わった。今日も怒鳴ってしまった。などと後悔ばかりということもあると思います。怒りや悲しみが湧いてきて、それを子どもにぶつけてしまわないように自分自身のイライラに気づく必要があります。心に余裕のないときは、問題に近づきすぎて俯瞰できない状況なので、安全を確かめたうえで、一旦距離を置く。窓を開けて部屋の空気を入れ替える。深呼吸をする。など、自分なりに問題だけに囚われないようにすることが必要になります。よく、腑に落ちる。といいますが、頭の中のモヤモヤを腹に落とすには「そうはいっても、この子がいるおかげで日々の成長が嬉しい。」と感謝できることを探すようにします。ちょうど、洗面台いっぱいのヘドロが下水管を流れないときに、流れないヘドロにフォーカスするよりも、細い下水管を太くするほうがきれいに流れて洗面台がスッキリするのと似ています。下水道管を太くする方法は「感謝」でしょう。〇〇してくれない!あの子のせいで!よりも、「あの子がいてくれたおかげで。元気に育ってくれたおかげで。」と感謝できることを探してみると不思議とスッキリするものです。
二つのマインドセット
1. 固定マインドセット(Fixed Mindset)
• 「自分の能力は生まれつき決まっている」と考える。
• 失敗を避けがちで、新しい挑戦に消極的。でっかい挑戦の先には、成功か学びしかない。失敗とは何もしないことをいう。
2. 成長マインドセット(Growth Mindset)
• 「努力次第で能力は伸ばせる」と考える。
• 失敗を学びの機会と捉え、挑戦を続ける。
成功する人や、柔軟に生きている人は「成長マインドセット」を持っている。
内 容
子育て上手な人のマインドセット
教職43年の経験と、我が子の、孫の子育てから見えてきたこと
自己紹介:現役幼稚園園長 小学校・中学校の校長 高等学校保健体育教諭 文部科学省派遣教員(ニューヨーク・香港)他
マインドセット(mindset)とは、物事に対する「考え方の枠組み」や「思考の習慣」のことを指します。
その人が持っている価値観や信念、思考パターンのことです。
例えば、同じ状況でも人によって捉え方が違うのは、マインドセットが異なるからです。
• 「失敗=成長のチャンス」と考える人は、挑戦を続ける。
• 「失敗=恥ずかしいこと」と考える人は、新しいことに挑戦しにくくなる。
つまり、どんなマインドセットを持つかによって、行動や結果が変わってくるのです。
二つのマインドセット
1. 固定マインドセット(Fixed Mindset)
• 「自分の能力は生まれつき決まっている」と考える。
• 失敗を避けがちで、新しい挑戦に消極的。でっかい挑戦の先には、成功か学びしかない。失敗とは何もしないことをいう。
2. 成長マインドセット(Growth Mindset)
• 「努力次第で能力は伸ばせる」と考える。
• 失敗を学びの機会と捉え、挑戦を続ける。
成功する人や、柔軟に生きている人は「成長マインドセット」を持っていることが多い。
Q,マインドセットは変えられる?
マインドセットは意識的に変えることができます。例えば、普段の言葉を変えるだけでも効果があります。
• 「これは無理」→「どうすればできるかな?」
• 「自分には才能がない」→「今はできなくても、練習すれば上達するかも」
このように、日々の考え方を少しずつ変えていくことで、より前向きなマインドセットを育てることができます。
子育て、子どもを観察するときに、現象や結果だけを見てしまいがち。
モンテッソーリ教育では、子どもは何もできない存在ではなく、環境を整えてやれば自ら育つ力がどの子にもあると考えます。その価値観が氷山の9割の水の中にある潜在意識です。
氷山のモデル(Iceberg Model)は、マインドセットと深く関係しています。
Q,氷山のモデルとは?
氷山のモデルは、目に見える行動の背景には、目に見えない深いレベルの思考や価値観が影響している、という考え方を示したものです。
例:氷山のイメージ
• 水面の上(見える部分):行動・言葉・態度
• 水面の下(見えない部分):思考・信念・価値観・マインドセット
つまり、私たちの行動や言葉は、「その下にあるマインドセット(考え方の枠組み)」によって決まっているのです。
Ex.
氷山のモデルとマインドセットの関係
たとえば、子育てにおいて「子どもをすぐに叱ってしまう」という行動があるとします。
① 表面に見える行動(氷山の上)
• すぐに「ダメ!」と言ってしまう
• 子どものミスを厳しく指摘する
② 行動の背景にあるマインドセット(氷山の下)
• 「子育ては親の責任だから、ちゃんとしなきゃ」
• 「子どもを甘やかすと将来困る」
• 「失敗は良くないことだ」
このように、行動の根本にはマインドセットがあり、もしマインドセットを変えれば行動も変わる可能性があります。
③ マインドセットを変えると…
もし「失敗は学びのチャンス」というマインドセットを持てたら?
• 「ダメ!」ではなく、「どうすればうまくいくかな?」と問いかけられるようになる。
• 子どもの失敗を責めるのではなく、一緒に考える姿勢が生まれる。
氷山の下にあるマインドセットを意識的に変えることで、行動や子育ての仕方も変わる。まとめ
氷山のモデルを理解すると、「なぜ自分はこういう行動をとるのか?」を深掘りし、より良いマインドセットを育てるヒントになります。子育てだけでなく、仕事や人間関係にも応用できる考え方です。
子どもの権利条約とマインドセットの共通点。
1. 子どもを「主体」として尊重する考え方
子どもの権利条約では、子どもを「保護される存在」ではなく、「権利を持つ主体」として尊重することが基本理念です。
• 例えば、第12条では「子どもが自分の意見を表明し、それが尊重される権利」が保障されています。
• これは、「子どもにも意思があり、尊重されるべき存在だ」というマインドセットが前提になっています。
つまり、親のマインドセットが「親が決めるべき」「子どもは指示に従うもの」だと、条約の理念とズレが生じます。逆に、「子どもも一人の人間として尊重する」マインドセットを持つと、条約の理念に沿った子育てがしやすくなります。
2. 子どもの最善の利益を考える(第3条)
第3条には、「子どもに関わるあらゆることにおいて、最も重要なのは子どもの最善の利益である」と書かれています。
• これも、子ども中心の考え方を持つマインドセットが必要です。
• 例えば、子どもの意見を聞かずに親がすべて決めるのではなく、「この決定は本当に子どもにとって最善か?」と考える姿勢が大切になります。
3. 成長マインドセットと「生きる権利・育つ権利」
• 子どもの権利条約では、子どもが健康に成長し、教育を受け、能力を伸ばせる環境を保障することが求められています。
• これは、「子どもは成長し、学び、可能性を広げられる存在である」という成長マインドセットと共通する考え方です。
まとめ:マインドセットを変えることで子ども条約を実践しやすくなる
• 氷山モデルと同様、親の行動の背景には子ども観(マインドセット)が影響します。
• 「子どもは守られるべき存在」という固定的な考えから、「子どもは権利を持ち、成長できる主体」という考えに変わると、条約の理念に沿った子育てがしやすくなります。
• マインドセットを変えることは、子どもの権利を守る第一歩になります。
このように、子どもの権利条約とマインドセットは、「子どもをどう捉えるか?」という根本的な考え方の部分でつながっていると言えますね。
マズローの欲求階層説と子育てのマインドセットには多くの共通点があります。マズローの理論によると、人間の欲求は5段階のピラミッドのようになっており、低いレベルの欲求が満たされると、次のレベルの欲求を求めるようになります。
Q,マズローの欲求階層説と子育ての関係は?
① 生理的欲求
【食事・睡眠・健康】
• まず、子どもが成長するためには基本的な生活の安定が必要。
• 親のマインドセット:「子どもが安心して生きられる環境を整えることが最優先」
• 子どもが成長するためには、まず「衣食住」が安定していることが必要。
• 十分な睡眠・栄養・運動が確保されていないと、心の発達にも影響を与える。
② 安全の欲求
【安心できる環境・経済的安定・身の安全】
• 子どもは、身体的・精神的に安全であると感じることで、安心して成長できる。
• 「怒られるかもしれない」「家が不安定」「親の機嫌をうかがう」と感じると、学びや挑戦が難しくなる。
• 親のマインドセット:「子どもが安心できる環境を作ることが大事」
• 心理的に安心できる環境があってこそ、子どもは自分らしく行動できる。
③ 社会的欲求
【愛情・家族の絆・友達とのつながり】
• 子どもは「自分は愛されている」「受け入れられている」と感じることで、自己肯定感が育つ。
• スキンシップや、子どもの話をしっかり聞くことが重要。
• 親のマインドセット:「子どもの気持ちを尊重し、愛情をしっかり伝える」
④ 承認の欲求
【自信・達成感・他者からの尊重】
• 「できた!」「認められた!」という経験が、子どもの自信につながる。
• 「頑張れば成長できる」という成長マインドセットが大切。
• 親のマインドセット:「子どもの努力や成長を認め、成功体験を増やす」
⑤ 自己実現の欲求
【自分らしさ・夢の実現】
• ここまでの欲求が満たされると、「自分らしく生きたい」「好きなことを追求したい」という欲求が生まれる。
• 子どもが自分の興味を持ち、夢を実現するためのサポートが大切。
• 親のマインドセット:「子どもの個性や才能を尊重し、自由に成長させる」
共通点とポイント
✅ 子どもが安心できる環境(①②)を整えることが最優先
✅ 愛情や信頼関係(③)があってこそ、自信(④)が育つ
✅ 最終的には子どもの自己実現(⑤)を支えることが親の役割
このように、マズローの欲求階層説と子育てのマインドセットは、「子どもが成長するための段階的なプロセス」という点で共通しています。親のマインドセットを意識することで、子どもの成長をより良くサポートできます。
マズローの欲求階層説と子育てのマインドセットには、共通する考え方が多くあります。特に、「子どもの成長には段階がある」「基本的な欲求が満たされることで、次のレベルに進める」という点が共通しています。
根拠・関連する活動歴
現役幼稚園園長として、モンテッソーリ教育(藤井聡太しやビルゲイツなどが学んだ教育)実践中。
小学校・中学校の校長 高等学校保健体育教諭 文部科学省派遣教員(ニューヨーク・香港)他 人権や生徒指導、全国の学校にSSW・スクールソーシャルワーカーを導入する際の文部科学省モデルとなるなど








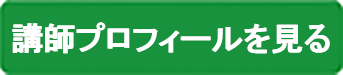


 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました


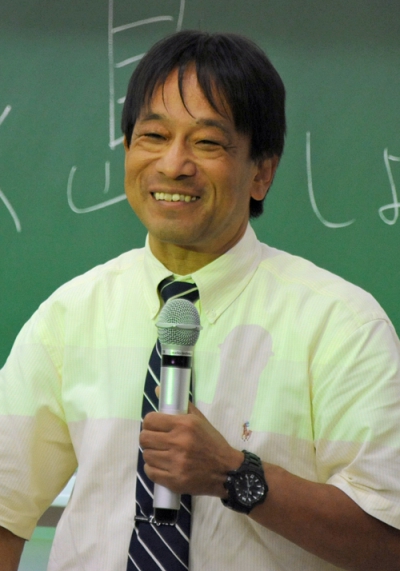










業務外の講師への取次は対応しておりません。