想定する対象者
大学・高校…教育的観点から国際政治やルール形成を学ぶ素材として有用
官公庁・自治体 …EU政策との整合性・国際基準への対応・地域国際化戦略のヒント
企業関係者・・・ 規制準拠による競争優位・CSR・サプライチェーン管理への影響
市民大学・社会連携・・・欧州統合という壮大な実験から学ぶ民主主義と連帯の力
本講演では、欧州統合の歩みを戦後の歴史的背景から振り返りつつ、現在のEU制度と政策形成のメカニズムを概説します。とりわけ、欧州委員会・欧州議会・理事会などの主要機関の役割と相互作用、そして政策決定における官僚的・合議的な特性に焦点を当てます。さらに、域外企業にも波及する「ブリュッセル効果(Brussels Effect)」の実態を明らかにし、GDPRやグリーンディール、AI規制といった具体的政策が日本企業や官民の戦略にどのような影響を与えているのかを検討します。国際行政、企業戦略、高校・大学教育、自治体の国際化政策に関心のあるすべての方に向けて、EUの現代的意義をわかりやすく紹介します.
提供する価値・伝えたい事
.【1】大学・高校(教員・学生・進路支援担当)への価値
グローバル市民教育と主権・統合のリアルケーススタディ
→ EUは「国家を超えた統治」の生きた教材。地理・公民・国際関係・政治経済・SDGsの横断学習に最適。
進路の羅針盤としてのルールメイカーEUの姿
→ 国際機関志望、外資系、国際NGO、政策官僚などのキャリア形成に必要な“規範と実務”のバランス感覚を育む。
模擬講義に適した学術と実務をつなぐテーマ構成
→ 歴史、制度、政策、そして日本との接点という4層構造で学際的な知的好奇心を刺激。
【2】官公庁・自治体の政策担当者への価値
EUは「先に進む実験室」:日本の制度設計のヒント
→ グリーンディール、デジタル主権、地域政策、社会的包摂などにおける欧州の挑戦から、制度設計の参考が得られる。
「ブリュッセル効果」に見るソフト・パワーの威力
→ 国際規格に自国がどう適応・関与するか。ルール形成過程に日本がどう食い込めるかの戦略的視点を提供。
地方自治体の国際連携の道標に
→ 日EU地方間交流(地域政策・環境都市協力・文化外交等)の可能性を示し、地域のグローバル化施策の根拠に。
【3】企業関係者への価値
グローバルスタンダードとしてのEU法の波及力
→ GDPR、AI Act、CSRDなど、EU発の規制は“事実上の世界標準”。日本企業も無関係ではいられない。
企業価値と規制対応が一体化する時代への備え
→ ESG・デジタル・サステナビリティにおいて、EU規制の理解が経営判断やリスク回避、ブランド構築に不可欠。
現場と経営層をつなぐ「翻訳者」としての知見
→ 経営企画部門や国際事業部にとって、EU制度の理解は単なる法令対応を超えた戦略的武器となる。
【4】市民大学・社会連携講座への価値
“戦争をしない地域”という理念とその実現のプロセス
→ 欧州統合の根源的意義にふれることで、「平和・共生・民主主義」を地域社会の文脈で再考する契機に。
「制度」の見える化を通じた民主主義教育
→ 市民参加や合意形成の仕組みをEUと比較することで、日本の課題も浮き彫りにし、熟議民主主義のリテラシーを育む。
世界とつながる自治体・NPOの役割を再発見
→ 地域とEUの協働事例(環境・文化・青少年交流など)を紹介し、ローカルからのグローバル参画の可能性を示す。
講演の内容:なぜ今EUを語るのか
「遠い地域」から「ルールでつながる隣人」へ
→ データ、環境、AI、労働などあらゆる領域で、EUのルールが日本社会に“静かに浸透”している現実を描く。
「民主主義と統治の実験室」としての価値
→ 欧州統合は失敗と成功を繰り返しながら進む「開かれた制度進化」。日本の行政・企業にも学びが多い。
「グローバル公共圏」の形成に関与する視点の提供
→ 日本が受け身でなく、EUと「共にルールをつくる主体」になるために必要な視座を共有。
歴史・制度・政策・日本との接続という全方位構成
→ 初学者にも、専門家にも、理論にも実務にも接続可能なフレームで構成。汎用性と深みを両立。
内 容
講演構成案(60~90分想定)
1. 序章:なぜ今、EUを学ぶのか?
世界的なルールメイカーとしてのEU
「距離の近い外国」=ルールでつながる時代の到来
2. 欧州統合の歴史:戦争から平和へ
ECSC(石炭鉄鋼共同体)からEUへ
東方拡大とユーロ導入、制度的深化の系譜
3. EUの制度構造:三つの柱と複雑なバランス
欧州委員会、欧州議会、EU理事会の役割
市民代表性と官僚制の交差点
マルチレベル・ガバナンス(多層的多元的統治)
4. EUの政策形成過程:調整・協議・実施の力学
欧州委員会の立法イニシアティブ
ロビイングと市民社会の参加
実施の段階における加盟国との役割分担
5. ブリュッセル効果と日本企業への影響
「自律的規制移転」のメカニズムとは
GDPR、CSRD、AI Actの事例分析
日本企業の対応と競争戦略(例:トヨタ、ソニー、商社)
6. 日本にとってのEUの意義
経済的・制度的つながり(EPA・SPS・OECD協力)
官公庁・自治体・企業・教育機関のEU連携の可能性
高校・大学での「主権と統合」「地域と共生」教育への応用
7. 結び:EUから見える「ルールによるグローバル化」
ルールメイキングにどう関わるか
地方自治体・教育現場・企業の役割と
根拠・関連する活動歴
全国自治体の市民大学。社会連携講座での講演、大学・高校での講演、官公庁・経済団体、国際交流基金での講演、国会議員対象の講演会、千葉CSTVでの講演出演の実績。








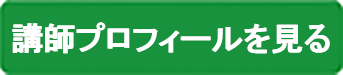


 講師候補」に登録されました
講師候補」に登録されました













業務外の講師への取次は対応しておりません。